粉瘤の手術は日帰りで可能?費用と治療法を徹底解説
粉瘤とは?症状と原因について
粉瘤(ふんりゅう)は「表皮嚢腫(ひょうひのうしゅ)」や「アテローム」とも呼ばれる良性の皮膚腫瘍です。皮膚の下に袋状の構造(嚢腫)が形成され、その内部に角質や皮脂などの老廃物がたまることで発生します。
粉瘤は全身のあらゆる部位に発生する可能性がありますが、特に顔、首、背中、耳の後ろなどに好発します。初期段階では皮膚の下に数ミリ程度のやわらかいしこりとして現れ、痛みやかゆみを伴わないことがほとんどです。
触れるとコリコリとした感触があるのが特徴で、中央に小さな穴(へそ)があることも多いです。この穴から押すと独特な悪臭を伴う白い粥状の物質が出てくることがあります。これは脂肪ではなく、垢のカタマリなのです。
放置すると徐々に大きくなり、皮膚表面にドーム状の隆起として現れます。さらに、細菌感染を起こすと炎症が生じ、患部が赤く腫れて熱を持ち、強い痛みや化膿を伴うことがあります。この状態を「炎症性粉瘤」や「感染性粉瘤」と呼びます。
粉瘤の原因
粉瘤の明確な原因はまだ完全には解明されていませんが、以下のような要因が関与していると考えられています。
- 毛穴の閉塞
- 皮膚への外傷や摩擦
- ウイルス感染(ヒトパピローマウイルスなど)
- 遺伝的要因
本来であれば剥がれ落ちていくはずだった皮膚が、皮膚の内部にめり込んで袋状の腫瘍を形成し、そこへ皮脂や角質が溜まって腫瘍が形成されます。
毛穴があるところに生じるケースがよく見られますが、毛穴がない部位でも起こります。そのため、小さな傷などをきっかけとして皮膚が内側へめり込むことが原因ではないかと言われています。

粉瘤の治療法と手術方法
粉瘤は、袋状の構造(嚢腫)の被膜ごと完全に取り除かない限り、治ることはありません。そのため、治療には外科的な摘出手術が必要になります。
手術には主に以下の2つの方法があり、いずれも局所麻酔下で行う日帰り手術が可能です。それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。
切開法
粉瘤のある部分の皮膚を大きめに切開し、内容物と被膜を一体で摘出する方法です。従来から行われている標準的な手術方法で、以下のような特徴があります。
- 粉瘤の大きさに合わせて皮膚にマーキングを行い、皮膚のシワ方向を考慮した紡錘形に切開します
- 切開線は粉瘤の長径と同じか、少し大きめになります
- 粉瘤の袋(カプセル)を破らずに全摘出することで、再発を防ぎます
- 摘出後は適切な皮下縫合と真皮縫合を行い、皮膚を軽く盛り上がる程度に縫合します
- 皮膚表面は傷跡が目立たないように細めの縫合糸で軽く合わせます
くり抜き法に比べて切開範囲が広くなりますが、炎症を起こしている粉瘤や、被膜が癒着している場合でも対応可能で、再発リスクが低いのが特徴です。
くり抜き法(へそ抜き法)
専用の円筒状の器具やメスを使い、粉瘤の中央に小さな穴を開けて、内容物を取り出し、その後に袋状の被膜を丁寧に摘出する方法です。
- 皮膚生検用のデルマパンチを使って、粉瘤のへそ部分に穴を開けます
- まず粉瘤の内容物(垢・皮脂)などを排出します
- 小さな穴から縮んだ皮膜(粉瘤の袋部分)を剥離、摘出します
- 切開範囲が小さく傷跡が目立ちにくいのが特徴です
- 術後の回復も早いとされています
ただし、くり抜き法にはいくつかのデメリットもあります。粉瘤の袋を完全に取り除けない場合があり、その場合は再発のリスクが高まります。また、大きな粉瘤や炎症を起こしている粉瘤、皮膚が厚い部位の粉瘤には適していません。
粉瘤の日帰り手術は可能?手術の流れと注意点
粉瘤の手術は、基本的に日帰りで行うことが可能です。局所麻酔を使用するため、全身への負担も少なく、手術時間も比較的短時間で済みます。
日帰り手術には、入院の必要がなく、仕事や日常生活への影響を最小限に抑えられるというメリットがあります。また、費用面でも入院手術に比べて安く抑えられます。
日帰り手術の流れ
粉瘤の日帰り手術は、一般的に以下のような流れで行われます。
- 診察・診断:医師が症状を確認し、粉瘤であるかどうかを診断します。手術について説明を受け、同意した上で手術へと進みます。
- 局所麻酔:粉瘤の大きさに合わせて周囲にマーキングをしてから、局所麻酔を行います。麻酔が効いてから切開を行うので、痛みはほとんど感じません。
- 手術(切開法またはくり抜き法):粉瘤の状態や大きさに応じて、適切な手術方法で摘出を行います。
- 縫合・処置:切開法の場合は傷口を縫合します。くり抜き法の場合は基本的に縫合は不要ですが、必要に応じて縫合することもあります。
- 術後の説明:傷口の処置方法や注意点について説明を受けます。
手術時間は粉瘤の大きさや手術方法によって異なりますが、多くの場合15分〜1時間程度で終了します。術後はすぐに帰宅することができます。
日帰り手術の注意点
日帰り手術を受ける際には、以下のような点に注意しましょう。
- 手術当日は運転を避け、公共交通機関を利用するか、家族に送迎してもらうことをお勧めします
- 手術後は傷口を清潔に保ち、医師の指示に従って適切に処置しましょう
- 傷口が完全に治るまでは激しい運動や入浴(シャワーは可能な場合が多い)を控えましょう
- 術後に異常な痛みや出血、腫れなどがある場合は、すぐに医療機関に相談しましょう
粉瘤が炎症を起こしている場合は、まず炎症を抑える治療を行い、炎症が落ち着いてから手術を行うことが一般的です。炎症がある状態での手術は、感染リスクが高まるだけでなく、粉瘤の袋を完全に取り除くことが難しくなり、再発の原因になることがあります。

粉瘤手術の費用と保険適用について
粉瘤の治療を検討する際に気になるのが費用です。粉瘤の手術は健康保険が適用されるため、経済的な負担を抑えて治療を受けることができます。
診察、検査、診断、手術、病理検査などの医療行為は、すべて健康保険の適用対象となります。また、民間の医療保険にご加入の場合は、契約内容によって手術給付金などの支払い対象となることもあります。
粉瘤手術の費用の目安
粉瘤の手術費用は、手術部位が「露出部(顔、首、肘から指先まで、膝から足先まで)」か「非露出部(露出部以外)」かによって異なります。また、粉瘤の大きさによっても費用に差が生じます。
露出部(顔、首、肘から指先まで、膝から足先まで)の場合の費用目安は以下の通りです(3割負担の場合):
- 直径2cm未満:5,000〜10,000円程度
- 直径2〜4cm:11,000〜16,000円程度
- 直径4cm以上:13,000〜18,000円程度
非露出部(露出部以外)の場合の費用目安は以下の通りです(3割負担の場合):
- 直径3cm未満:4,000〜9,000円程度
- 直径3〜6cm:10,000〜15,000円程度
- 直径6cm以上:12,000〜18,000円程度
1割負担の方の場合は、上記の3分の1程度の費用となります。なお、実際にかかる医療費は、手術費用のほかに、診察料・処方料、検査費用、病理検査費用なども含まれます。
生命保険の給付金について
粉瘤の手術を受ける場合、個人で生命保険会社や共済組合の医療保険や医療特約に加入されている方は、保険商品によっては手術給付金の対象となることがあります。
粉瘤の手術の場合の術式名は、「皮膚・皮下腫瘍摘出術」となります。給付金が受けられる可能性がある場合は、事前に保険会社に確認し、申請に必要な書類を準備しておくとよいでしょう。
粉瘤の手術を受けるタイミングと医療機関の選び方
粉瘤は良性の腫瘍であるため、生命に関わる緊急性は基本的にありません。しかし、放置すると徐々に大きくなり、炎症を起こすリスクが高まります。また、稀ですが化膿や炎症を繰り返すと粉瘤の袋の壁から皮膚癌が発生することもあります。
粉瘤に気づいたら、むやみに触らず、できるだけ早めに医療機関を受診することをお勧めします。特に以下のような場合は、早めの受診が望ましいです。
- 粉瘤が急に大きくなってきた場合
- 痛みや熱感、発赤などの炎症症状が現れた場合
- 粉瘤が破れて内容物が出てきた場合
- 粉瘤が目立つ場所にあり、見た目が気になる場合
粉瘤が大きくなってから摘出すると、傷跡も目立ちやすくなります。小さいうちに日帰り手術で治療することをお勧めします。
適切な医療機関の選び方
粉瘤の手術を受ける医療機関を選ぶ際には、以下のようなポイントを考慮するとよいでしょう。
- 専門性:皮膚科、形成外科、外科などの専門医がいる医療機関を選びましょう
- 手術実績:粉瘤の手術実績が豊富な医師がいる医療機関が望ましいです
- 設備:清潔な手術室や適切な医療機器が整っているかどうかも重要です
- アクセス:術後の通院も考慮して、通いやすい場所にある医療機関を選びましょう
- 対応:丁寧な説明と患者の不安に寄り添う対応をしてくれる医療機関が理想的です
当院(大阪消化器内科・内視鏡クリニック難波院)では、肛門科レディース外来・粉瘤手術を行っており、女性医師による診療も可能です。大阪メトロ御堂筋線・千日前線「なんば駅」からすぐの駅直結ビル内にあり、アクセスも良好です。

粉瘤手術後の経過と注意点
粉瘤の手術後は、適切なケアを行うことで傷跡を最小限に抑え、スムーズな回復を促すことができます。ここでは、手術後の経過と注意点について解説します。
手術後の経過
粉瘤の手術後の回復期間は、手術方法や粉瘤の大きさ、部位によって異なりますが、一般的には以下のような経過をたどります。
- 術直後〜数日:麻酔の効果が切れると、軽度の痛みや腫れが生じることがあります。処方された痛み止めを服用し、安静にすることで症状は徐々に改善します。
- 1週間程度:腫れや痛みはほとんど治まります。切開法で縫合した場合は、この頃に抜糸を行うことが多いです。
- 2〜4週間:傷口は徐々に治癒し、赤みが薄れていきます。この時期は傷跡が目立つことがありますが、時間の経過とともに目立たなくなっていきます。
- 数ヶ月〜1年:傷跡は徐々に薄くなり、最終的な状態に落ち着きます。
術後の注意点
手術後は以下のような点に注意して生活することで、合併症を防ぎ、きれいな傷跡に治すことができます。
- 傷口のケア:医師の指示に従って、傷口を清潔に保ちましょう。入浴やシャワーについても医師の指示に従ってください。
- 抜糸まで:抜糸までは傷口を濡らさないようにし、激しい運動や傷口に負担がかかる動作は避けましょう。
- 日常生活:手術部位によっては、一定期間、重い物を持つ、腕を高く上げるなどの動作を控える必要があります。
- 傷跡のケア:抜糸後は、医師の指示に従って傷跡のケアを行いましょう。日焼けを避け、必要に応じて傷跡用のクリームを使用することで、目立ちにくい傷跡に仕上がります。
術後に以下のような症状が現れた場合は、すぐに医療機関に相談しましょう。
- 強い痛みや腫れが続く
- 傷口から膿や悪臭のある分泌物が出る
- 38度以上の発熱がある
- 傷口が開いてしまった
これらの症状は感染や合併症の可能性があるため、早めの対応が必要です。
粉瘤の予防と自己管理について
粉瘤は完全に予防することは難しいですが、いくつかの対策を講じることで発生リスクを低減したり、早期発見したりすることができます。
粉瘤の予防策
粉瘤の発生を完全に防ぐことはできませんが、以下のような対策が有効と考えられています。
- 皮膚の清潔を保つ:毎日のシャワーや入浴で皮膚を清潔に保ちましょう。特に皮脂の分泌が多い部位はしっかり洗いましょう。
- 適切なスキンケア:肌に合った洗顔料や保湿剤を使用し、肌のバリア機能を保ちましょう。
- 摩擦や圧迫を避ける:きつい衣服や装飾品による皮膚への摩擦や圧迫は避けましょう。
- 外傷に注意:皮膚への小さな傷も粉瘤の原因になることがあるため、注意しましょう。
自己チェックの重要性
粉瘤は早期に発見することで、小さいうちに治療することができます。定期的な自己チェックを行うことで、早期発見・早期治療につなげることができます。
入浴時などに全身の皮膚をチェックし、以下のような変化がないか確認しましょう。
- 皮膚の下にコリコリとした小さなしこり
- 皮膚表面のドーム状の隆起
- 中央に小さな穴(黒点)がある隆起
- 押すと白い内容物が出てくる部位
これらの症状に気づいたら、自己判断せずに医療機関を受診しましょう。特に以下のような場合は、早めの受診が望ましいです。
- 急に大きくなってきた
- 痛みや熱感、発赤などの炎症症状がある
- 見た目が気になる部位にある
粉瘤は良性の腫瘍ですが、放置すると大きくなったり炎症を起こしたりするリスクがあります。小さいうちに治療することで、手術の負担も少なく、傷跡も目立ちにくくなります。
まとめ
粉瘤は日帰り手術で治療可能な良性の皮膚腫瘍です。健康保険が適用されるため、経済的な負担も比較的少なく治療を受けることができます。
粉瘤に気づいたら、自己判断で潰したり放置したりせず、専門医を受診することが大切です。特に炎症を起こす前の早期治療が、再発リスクの低減や傷跡の最小化につながります。
当院(大阪消化器内科・内視鏡クリニック難波院)では、粉瘤の日帰り手術に対応しています。お気軽にご相談ください。
詳細は大阪消化器内科・内視鏡クリニック難波院の公式サイトをご覧ください。
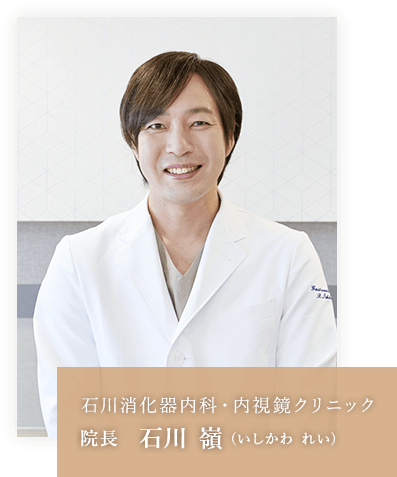
著者情報
理事長 石川 嶺
経歴
| 近畿大学医学部医学科卒業 |
| 和歌山県立医科大学臨床研修センター |
| 名古屋セントラル病院(旧JR東海病院)消化器内科 |
| 近畿大学病院 消化器内科医局 |
| 石川消化器内科内視鏡クリニック開院 |







