粉瘤は自然に治る?放置のリスクと正しい対処法
粉瘤とは?基本的な特徴と症状
皮膚の下に突然しこりのようなものを見つけたとき、それは「粉瘤(ふんりゅう)」かもしれません。粉瘤は、皮膚の内側に袋状の構造物ができ、その中に角質や皮脂などが溜まってできる良性の腫瘍です。
アテロームや表皮嚢腫(ひょうひのうしゅ)とも呼ばれるこの症状は、見た目の問題だけでなく、放置すると様々なリスクを伴います。
粉瘤の特徴的な症状としては、皮膚の下に数ミリから数センチの大きさのしこりができることが挙げられます。触ると弾力があり、動かせるものが多いです。中央には黒い点(開口部)が見られることがあり、ここから内容物が排出されることもあります。
全身のどこにでもできる可能性がありますが、特に顔、首、背中、耳の後ろなどの皮脂腺が多い部位にできやすい傾向があります。
どうして粉瘤ができるのでしょうか?
粉瘤の原因は明確には解明されていませんが、毛穴の詰まり、外傷、ウイルス感染などが関係していると考えられています。体質的に粉瘤ができやすい方もおり、複数の粉瘤が発生するケースも少なくありません。

粉瘤は自然に治る?真実と誤解
「粉瘤は放置していれば自然に治るのではないか」と考える方も多いでしょう。結論から言うと、粉瘤は自然に治ることはほとんどありません。
粉瘤は皮膚の下に袋状の組織が形成され、その内部に皮脂や垢などの老廃物が蓄積することで発生します。この袋(カプセル)が存在する限り、内容物は排出されず、むしろ徐々に蓄積していくことになります。
放置すると、老廃物が蓄積し、皮膚の盛り上がりが徐々に大きくなっていきます。小さな粉瘤でも、時間の経過とともに成長し、見た目の問題が大きくなることがあります。
また、粉瘤を自分で潰そうとする方もいますが、これは危険な行為です。無理に圧迫すると、内部の老廃物が皮膚の中に漏れ出し、異物反応を引き起こして炎症が生じることがあります。
「でも、小さな粉瘤なら自然に消えることもあるのでは?」
確かに、非常に小さな初期段階の粉瘤が自然に消退するケースもゼロではありません。しかし、それはごく稀なケースであり、多くの場合は徐々に大きくなっていくと考えるべきです。
粉瘤を放置するリスクとは?
粉瘤を放置することで、いくつかの重大なリスクが生じる可能性があります。これらのリスクを理解することで、適切な対処の重要性が見えてきます。
まず最も一般的なリスクは、粉瘤が徐々に大きくなることです。初期段階では数ミリ程度の小さなしこりでも、放置すると数センチから、稀に野球ボール大にまで成長することがあります。
次に深刻なのが、炎症を起こすリスクです。粉瘤に炎症が生じると、表面が赤くなり、痛みを伴うようになります。これが炎症性粉瘤です。
炎症が進むとどうなるでしょうか?
赤みが拡大し、痛みも強くなり、袋の内容物が膿となってブヨブヨとしてきます。腫れが限界に達すると、粉瘤が破裂して臭いドロドロの内容物が排出される場合もあります。
さらに危険なのが、細菌感染です。粉瘤を放置すると細菌感染する可能性があり、感染すると粉瘤の腫れたところが赤く痛みを伴うようになります。細菌感染したままさらに放置した場合、最終的には敗血症などの全身的な感染症になるリスクもあります。
悪性化のリスクも無視できません。粉瘤は基本的に良性ですが、経過が非常に長く、大きかったり、炎症を繰り返したりしたものは、ごくまれに悪性化したという報告もあります。特に、中高年齢層の男性の頭部、顔面、臀部の大きな粉瘤が急速に大きくなったり、表面の皮膚に傷ができたりする場合には注意が必要です。
炎症性粉瘤について知っておくべきこと
炎症性粉瘤とは、粉瘤に炎症が起こり、急速に大きくなって腫れや痛みを伴う状態のことを指します。通常の粉瘤と比べて、対処が必要な緊急性が高い状態です。
炎症性粉瘤の特徴は、赤みや熱感を伴うことが多く、触れると強い痛みがあります。炎症や化膿が進行すると、発熱や倦怠感といった全身症状が現れることもあるのです。
背中などの触れにくい部位では、炎症による腫れや痛みが生じて初めて粉瘤に気付くケースも少なくありません。
炎症性粉瘤を放置するとどうなるのでしょうか?
炎症性粉瘤は放置すると悪化し、感染が広がるリスクがあるため、早期の治療が重要です。治療方法としては、「抗生物質の内服」「切開排膿処置」「摘出手術」があり、症状の程度に応じて適切な治療が選択されます。
炎症が強くなり膿がたまってしまった状態では、膿を物理的に取り除かない限り炎症の改善が見込めません。そのため、切開排膿が必要になることがあります。
切開排膿は局所麻酔で行いますが、切開部分は縫わずに開放したままにします。排膿後に炎症が落ち着いてから、改めて粉瘤の摘出手術を行うことになります。

粉瘤の適切な治療法
粉瘤の治療には、どのような方法があるのでしょうか。粉瘤は、皮膚の下にできた袋状の組織を手術で完全に取り除かない限り完治しません。そのため、粉瘤の治療には外科的な摘出手術が必要になります。
粉瘤の摘出手術には、主にくり抜き法と切開法の二つの方法があります。それぞれの特徴を見ていきましょう。
くり抜き法
くり抜き法は、円筒状の専用器具(トレパン)やメスを使用し、粉瘤に小さな穴を開け、そこから老廃物などの内容物を取り出した後、袋状の組織である被膜を摘出します。
くり抜き法は、切開法と比較して切開する範囲が小さいため、傷が目立ちにくいのが特徴です。また、手術時間は5分〜20分程度と短く、患者さまの負担が少ない治療法といえます。
ただし、くり抜き法にはデメリットもあります。小さな穴からの操作となるため、粉瘤の袋を完全に取り除くことが難しい場合があります。袋が一部でも残ってしまうと、再発のリスクが高まります。
切開法
切開法では、粉瘤の真上の皮膚を切開し、粉瘤全体をまとめて摘出します。くり抜き法に比べて切開部分が大きくなりますが、再発のリスクが低いという特徴があります。
切開法は、さまざまなタイプの粉瘤に対応できる治療法です。大きな粉瘤や癒着が強い粉瘤、炎症を伴う粉瘤など、症状が進行した場合には、くり抜き法よりも切開法が適している場合があります。
どちらの手術方法が適しているかは、粉瘤の大きさや状態、場所によって異なります。医師と相談しながら、最適な治療法を選択することが大切です。
粉瘤の予防と日常生活での注意点
粉瘤の原因が明確に分かっておらず、予防方法に関しても確実な方法はわかっていません。しかし、粉瘤は皮下に角質や皮脂が溜まったものであるため、毎日お風呂に入って肌を清潔に保ったり肌への刺激を避けたりすることは決して無意味ではありません。
このような対策で粉瘤が必ず予防できるわけではありませんが、毎日の正しいスキンケアで粉瘤を含む肌トラブルを起こしにくい肌作りを目指しましょう。
粉瘤ができやすい部位としては、顔・首・耳周り・背中・おしりなどが挙げられます。これらの部位に共通する特徴として、皮脂腺が多く衣類による摩擦の影響を受けやすいことが関係しているようです。
粉瘤を見つけたら、どのように対処すべきでしょうか?
まず、自己判断で粉瘤を潰そうとするのは避けてください。無理に圧迫すると内容物が皮膚内に広がり、炎症を引き起こす可能性があります。
小さな粉瘤を見つけたら、早めに皮膚科や形成外科を受診することをおすすめします。小さいうちに適切な治療を受けることで、手術の負担も少なく、傷跡も目立ちにくくなります。
粉瘤が炎症を起こしている場合は、早急に医療機関を受診してください。赤みや痛み、熱感がある場合は、炎症が進行している可能性があります。

粉瘤と間違えやすい症状との見分け方
粉瘤と似ている病気には、いくつかの種類があります。正しい治療を受けるためにも、見分け方を知っておくことが大切です。
イボとの違い
イボの種類には、主にウイルス性のものと加齢や紫外線によってできるものがあります。ウイルス性の代表的なイボは尋常性疣贅(じんじょうせいゆうぜい)といい、ヒトパピローマウイルスが原因とされています。
イボは表面がブツブツして盛り上がり、多発する場合もあります。粉瘤との見分け方として、イボは短時間で違う部位にも生じやすい点が挙げられます。
ニキビとの違い
ニキビは毛穴の中に皮脂がつまることなどによって生じる慢性的な皮膚疾患です。毛穴の閉鎖と過剰な皮脂分泌、アクネ菌の増加が原因とされています。
ニキビと粉瘤の違いは、角質がたまる袋の中心になる穴が表面に見えるかどうかです。粉瘤が炎症を起こすとニキビよりも大型化することが多く、ニキビの場合は炎症がひどくなっても比較的小さいことが特徴です。
また、ニキビは放置すれば自然治癒することもありますが、粉瘤は放置しても自然治癒しません。
脂肪腫との違い
脂肪腫は、皮下組織の脂肪細胞が増殖してできる良性腫瘍です。粉瘤と同様に皮膚の下にしこりができますが、脂肪腫は柔らかく、押すとへこむような感触があります。
粉瘤は中央に黒い点(開口部)があることが多いですが、脂肪腫にはそのような特徴はありません。また、脂肪腫は炎症を起こすことが稀であるのに対し、粉瘤は炎症を起こしやすいという違いもあります。
まとめ:粉瘤の正しい対処法
粉瘤は自然に治ることはほとんどなく、放置すると徐々に大きくなったり、炎症を起こしたりするリスクがあります。小さな粉瘤でも、早めに適切な治療を受けることが重要です。
粉瘤の治療には、くり抜き法と切開法という二つの主要な手術方法があります。どちらの方法が適しているかは、粉瘤の大きさや状態、場所によって異なりますので、医師と相談しながら最適な治療法を選択しましょう。
粉瘤が炎症を起こしている場合は、早急に医療機関を受診することが必要です。炎症が進行すると、より複雑な治療が必要になることがあります。
日常生活では、肌を清潔に保ち、過度な刺激を避けることで、肌トラブルを予防する意識を持つことも大切です。
粉瘤かもしれないと思ったら、自己判断で潰そうとせず、専門医に相談することをおすすめします。早期発見・早期治療が、最小限の負担で粉瘤を治療する鍵となります。
当院では、粉瘤の診断から治療まで、患者様の状態に合わせた最適な治療を提供しています。粉瘤でお悩みの方は、お気軽に大阪消化器内科・内視鏡クリニック難波院までご相談ください。
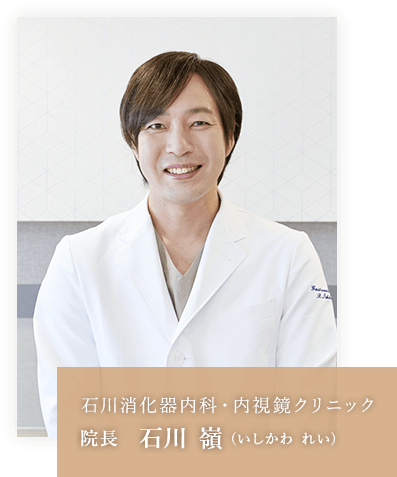
著者情報
理事長 石川 嶺
経歴
| 近畿大学医学部医学科卒業 |
| 和歌山県立医科大学臨床研修センター |
| 名古屋セントラル病院(旧JR東海病院)消化器内科 |
| 近畿大学病院 消化器内科医局 |
| 石川消化器内科内視鏡クリニック開院 |







