血便が出たら要注意!原因と緊急性の判断基準
血便が出たときの正しい対処法と緊急性の見極め方
トイレに行って便器が真っ赤になっていた。そんな経験をされた方は少なくないでしょう。血便を見つけたとき、多くの方が不安を感じるのは当然です。
血便には様々な原因があり、その中には緊急性の高いものから、比較的心配の少ないものまで幅広く存在します。重要なのは、どのような血便が危険信号なのかを正しく理解することです。
私は消化器内科医として20年以上にわたり、数多くの血便の症例を診てきました。この記事では、血便の種類や原因、そして何よりも「いつ病院に行くべきか」という判断基準についてお伝えします。

血便とは?種類と見分け方
血便とは、便に血液が混じった状態を指します。血便は大きく分けて「鮮血便」と「黒色便(タール便)」の2種類に分類されます。
鮮血便は、その名の通り鮮やかな赤色の血液が便に混じったものです。肛門に近い部位からの出血、つまり大腸や直腸からの出血によって生じることが多いです。便の表面に付着していたり、トイレットペーパーに血がついたりする状態です。
一方、黒色便(タール便)は、見た目が真っ黒でタールのように粘り気のある便のことです。食道や胃など、上部消化管からの出血が原因で起こります。血液が消化管内を通過する間に消化され、黒く変色するのです。
どうして血便の色が違うのでしょうか?
これは出血している場所によって決まります。肛門から近い場所で出血していれば鮮やかな赤色になり、肛門から遠くなるほど黒っぽくなります。つまり、血便の色を見ることで、どこから出血しているのかをある程度推測できるのです。
便潜血検査で見つかる血便
肉眼では見えないほどの微量な出血も、便潜血検査で発見されることがあります。これは大腸がん検診などで行われる検査です。
便潜血検査で陽性と判定された場合、必ずしも大腸がんというわけではありませんが、何らかの出血源があることを示しています。検査で陽性となった場合は、原因を特定するために大腸カメラ検査を受けることが推奨されます。
実際、便潜血検査で陽性となった方に大腸カメラ検査を行うと、3%弱の方に大腸がんが見つかっています。早期発見のためにも、検診で便潜血陽性と言われたら、必ず精密検査を受けましょう。
血便が出る主な原因疾患
血便の原因となる疾患は多岐にわたります。出血部位によって疑われる疾患も異なってきます。
まず、鮮血便を引き起こす主な疾患について見ていきましょう。
痔による出血(鮮血便)
最も頻度が高いのが痔からの出血です。いぼ痔(痔核)や切れ痔(裂肛)では、排便時の摩擦で出血することがあります。特徴的なのは、便の表面に鮮やかな赤い血液が付着していたり、トイレットペーパーに血がついたりすることです。
痔による出血は命に関わるものではありませんが、放置すると悪化することがあります。また、痔があるからといって血便の原因を全て痔と決めつけるのは危険です。
なぜでしょうか?
それは、痔と大腸がんなど他の疾患が同時に存在している可能性があるからです。「いつもの痔からの出血だろう」と思って放置し、大腸がんの発見が遅れるケースが少なくありません。血便が続く場合は、痔があっても一度消化器内科を受診することをお勧めします。
大腸・直腸の疾患(鮮血便)
大腸ポリープや大腸がんも鮮血便の原因となります。特に直腸がんでは、便に鮮血が混じることが多いです。大腸がんの初期には自覚症状がほとんどないため、血便が重要なサインとなります。
大腸憩室出血も鮮血便の原因となります。憩室とは腸の壁が部分的に外側に向かって袋状に突出したもので、加齢とともに増加します。この部分の血管が破れると、突然大量の鮮血便が出ることがあります。
炎症性腸疾患(鮮血便・粘血便)
潰瘍性大腸炎やクローン病などの炎症性腸疾患でも血便が見られます。特に潰瘍性大腸炎では、粘液と血液が混じった「粘血便」が特徴的です。腹痛や下痢を伴うことが多く、症状が長期間続く傾向があります。
これらの疾患は難病に指定されており、適切な治療を早期に開始することが重要です。血便に加えて腹痛や体重減少、発熱などの症状がある場合は、消化器内科の専門医による診察を受けることをお勧めします。
感染性腸炎(鮮血便・粘血便)
細菌やウイルスによる感染性腸炎でも血便が見られることがあります。腹痛や下痢、発熱を伴うことが多いのが特徴です。多くの場合、数日で自然に改善しますが、症状が強い場合や改善しない場合は医療機関を受診しましょう。
虚血性腸炎(鮮血便)
虚血性腸炎は、腸への血流が一時的に低下することで起こる疾患です。左側腹部の痛みと血便が特徴で、高齢者や動脈硬化のリスクがある方に多く見られます。
便秘時の強いいきみが原因となることもあります。軽症であれば自然に改善することもありますが、症状が強い場合は入院治療が必要になることもあります。

黒色便(タール便)の主な原因
次に、黒色便(タール便)を引き起こす主な疾患について見ていきましょう。
胃・十二指腸潰瘍(黒色便)
胃潰瘍や十二指腸潰瘍からの出血は、黒色便(タール便)の代表的な原因です。潰瘍から出血した血液が消化されることで、便が黒く変色します。
胃潰瘍や十二指腸潰瘍は、ストレスや不規則な生活習慣、ピロリ菌感染、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)の長期服用などが原因で発症します。上腹部の痛みや不快感を伴うことが多いですが、無症状のこともあります。
食道静脈瘤(黒色便)
肝硬変などの肝疾患がある方では、食道静脈瘤からの出血で黒色便が生じることがあります。食道静脈瘤が破裂すると大量出血を起こし、緊急処置が必要になることもあります。
肝疾患の既往がある方が黒色便を認めた場合は、食道静脈瘤からの出血の可能性を考慮し、速やかに医療機関を受診する必要があります。
薬剤の影響(黒色便)
鉄剤の服用でも便が黒くなることがあります。これは出血ではなく、鉄剤の影響によるものです。また、ビスマス製剤(胃薬の一種)の服用でも便が黒くなることがあります。
薬剤による黒色便は病的なものではありませんが、薬の服用と関係なく黒色便が出る場合は、上部消化管からの出血を疑い、医療機関を受診しましょう。
血便が出たときの緊急性の判断基準
血便を認めた場合、すぐに病院に行くべきか、様子を見ても良いのか、判断に迷うことも多いでしょう。ここでは、緊急性の高い血便の特徴について解説します。
すぐに受診すべき血便の特徴
以下のような特徴がある場合は、緊急性が高いと考えられますので、すぐに医療機関を受診してください。
- 大量の出血(コップ1杯以上の血液が出る)
- 黒色便(タール便)が続く
- 血便に加えて、ふらつき、冷や汗、意識がはっきりしないなどの症状がある
- 突然の激しい腹痛を伴う血便
- 繰り返す吐血と血便
これらの症状は、大量出血や重篤な疾患の可能性を示唆しています。特に、ふらつきや冷や汗などの症状は、ショック状態に陥っている可能性があり、命に関わる危険な状態です。
早めに受診すべき血便の特徴
緊急性は高くないものの、早めに受診した方が良い血便の特徴としては、以下のようなものがあります。
- 少量でも繰り返し血便がある
- 血便に加えて、腹痛や発熱が続く
- 血便に加えて、体重減少や食欲不振がある
- 便潜血検査で陽性と言われた
- 40歳以上で一度も大腸カメラを受けたことがない方の血便
これらの症状は、すぐに命に関わるものではありませんが、大腸がんなどの重大な疾患の可能性もあります。早期発見・早期治療のためにも、できるだけ早く医療機関を受診することをお勧めします。
様子を見ても良い血便の特徴
以下のような特徴がある場合は、緊急性は低いと考えられますが、症状が続く場合は受診をお勧めします。
- 排便時のみ少量の鮮血が付着し、それ以外の症状がない
- 痔の既往があり、いつもと同じような出血パターン
- 鉄剤などの薬剤服用中の黒色便
ただし、痔があるからといって血便の原因を全て痔と決めつけるのは危険です。痔と大腸がんなど他の疾患が同時に存在している可能性もあります。血便が続く場合は、一度消化器内科を受診することをお勧めします。

血便の検査と診断方法
血便の原因を特定するためには、適切な検査が必要です。ここでは、血便の診断に用いられる主な検査について解説します。
問診と視診
まず、医師による問診と視診が行われます。血便の性状(鮮血か黒色か)、量、頻度、他の症状(腹痛、発熱など)の有無などを詳しく聞かれます。
また、肛門の視診や指診(直腸診)も行われることがあります。これにより、痔や肛門周囲の疾患、直腸の腫瘤などを確認します。
問診で血便の状態を正確に伝えることが、適切な診断への第一歩です。可能であれば、血便の状態をスマートフォンなどで撮影しておくと、医師に正確に伝えることができます。
血液検査
血液検査では、貧血の有無や炎症反応の程度を確認します。大量出血があると貧血を起こし、ヘモグロビン値が低下します。また、炎症性腸疾患や感染性腸炎では、炎症反応(CRPや白血球数)が上昇することがあります。
血液検査の結果は、出血の程度や原因疾患の推定に役立ちます。
内視鏡検査(胃カメラ・大腸カメラ)
血便の原因を特定するための最も重要な検査が、内視鏡検査です。黒色便(タール便)の場合は胃カメラ、鮮血便の場合は大腸カメラが選択されることが多いですが、出血源が不明な場合は両方の検査が必要になることもあります。
内視鏡検査では、消化管の粘膜を直接観察することができるため、出血源の特定や病変の性状評価が可能です。また、必要に応じて組織検査(生検)や、ポリープ切除などの治療も同時に行うことができます。
CT検査
腹部CT検査は、腸管壁の肥厚や腫瘤、炎症の範囲などを評価するのに役立ちます。特に、大量出血や急性腹症の場合には、緊急でCT検査が行われることがあります。
CT検査は短時間で広範囲を検査できるメリットがありますが、小さな病変は見逃される可能性もあります。そのため、内視鏡検査と組み合わせて診断することが多いです。
便検査
便潜血検査や便培養検査も、血便の原因診断に役立ちます。便潜血検査は、肉眼では見えない微量の血液を検出するのに有用です。便培養検査は、感染性腸炎の原因となる細菌を特定するために行われます。
これらの検査結果を総合的に判断し、血便の原因を特定していきます。
血便の治療方法
血便の治療は、原因疾患によって大きく異なります。ここでは、主な疾患別の治療方法について解説します。
痔の治療
痔による出血の場合、軽症であれば保存的治療(座浴、軟膏塗布など)で改善することが多いです。症状が強い場合や保存的治療で改善しない場合は、ジオン注射や手術療法が検討されます。
痔の治療では、便通改善も重要です。食物繊維の摂取や十分な水分補給、規則正しい排便習慣を心がけましょう。
大腸ポリープ・大腸がんの治療
大腸ポリープは、内視鏡的ポリープ切除術で治療されることが多いです。当院では日帰りでの大腸ポリープ切除にも対応しています。
大腸がんの場合、早期であれば内視鏡的粘膜切除術(EMR)や内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)などの内視鏡治療が可能です。進行がんの場合は、外科的手術や化学療法、放射線療法などが検討されます。
炎症性腸疾患の治療
潰瘍性大腸炎やクローン病などの炎症性腸疾患では、5-ASA製剤(メサラジン)やステロイド薬、免疫調節薬、生物学的製剤などの薬物療法が中心となります。
これらの疾患は完全に治癒させることは難しいですが、適切な治療により症状のない寛解状態を維持することが可能です。定期的な通院と処方薬の継続が重要です。
胃・十二指腸潰瘍の治療
胃潰瘍や十二指腸潰瘍による出血の場合、プロトンポンプ阻害薬(PPI)などの酸分泌抑制薬が中心となります。ピロリ菌感染が確認された場合は、除菌治療も行われます。
大量出血や薬物療法で止血できない場合は、内視鏡的止血術や手術療法が検討されます。
大量出血時の緊急処置
大量出血によるショック状態では、まず全身状態の安定化が優先されます。輸液や輸血による循環動態の安定化を図りながら、出血源の特定と止血処置が行われます。
出血源が特定できれば、内視鏡的止血術や血管造影下の塞栓術、緊急手術などが検討されます。
大量出血は命に関わる危険な状態です。血便が大量にある場合や、ふらつき、冷や汗などのショック症状がある場合は、すぐに救急車を呼びましょう。

血便を予防するための生活習慣
血便の原因となる疾患を予防するためには、日常生活での心がけも重要です。ここでは、血便予防のための生活習慣について解説します。
食生活の改善
バランスの良い食事を心がけましょう。特に、食物繊維の摂取は便通改善に役立ち、痔や大腸疾患の予防につながります。野菜、果物、全粒穀物などを積極的に摂取しましょう。
また、過度の辛い食べ物や刺激物、アルコールの摂取は消化管粘膜を刺激し、炎症や出血のリスクを高める可能性があります。適度な摂取を心がけましょう。
適度な運動と水分摂取
適度な運動は腸の蠕動運動を促進し、便秘予防に役立ちます。また、十分な水分摂取も便を柔らかくし、排便を円滑にします。
特に高齢者は水分摂取が不足しがちです。意識して水分を摂るようにしましょう。
規則正しい排便習慣
便意を感じたら我慢せず、できるだけ早くトイレに行くようにしましょう。便意を我慢すると便が硬くなり、排便時に肛門に負担がかかるため、痔の原因となります。
また、排便時に強くいきむことも避けましょう。強いいきみは痔の悪化や虚血性腸炎のリスクを高める可能性があります。
定期的な健康診断
40歳以上の方は、年に1回は便潜血検査を含む健康診断を受けることをお勧めします。便潜血検査で陽性となった場合は、必ず精密検査(大腸カメラ)を受けましょう。
大腸がんは早期発見・早期治療が可能な疾患です。定期的な検診が早期発見の鍵となります。
まとめ:血便を見つけたらどうすべきか
血便は様々な疾患のサインとなり得るものです。その中には緊急性の高いものから、比較的心配の少ないものまで幅広く存在します。
大量の出血や、ふらつき、冷や汗などのショック症状を伴う場合は、すぐに救急車を呼びましょう。また、黒色便(タール便)や、腹痛、発熱を伴う血便も早めに医療機関を受診することをお勧めします。
痔があるからといって血便の原因を全て痔と決めつけるのは危険です。痔と大腸がんなど他の疾患が同時に存在している可能性もあります。血便が続く場合は、一度消化器内科を受診することをお勧めします。
当院では、日本内視鏡学会認定の内視鏡専門医による胃カメラ検査・大腸カメラ検査を提供しています。鎮静剤(麻酔)を使用した苦痛の少ない検査を心がけておりますので、血便でお悩みの方はお気軽にご相談ください。
健康な生活を送るためにも、血便という体からのサインを見逃さず、適切な対応を取りましょう。
詳しい情報や診療予約については、大阪消化器内科・内視鏡クリニック難波院のウェブサイトをご覧いただくか、お電話でお問い合わせください。
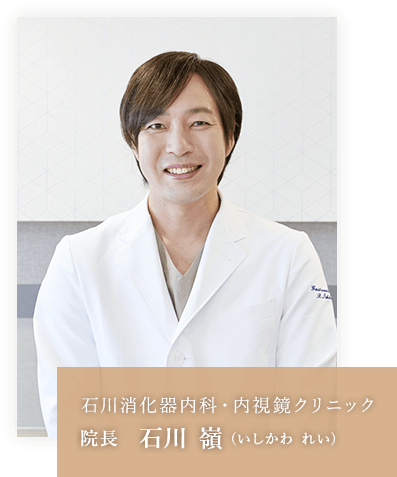
著者情報
理事長 石川 嶺
経歴
| 近畿大学医学部医学科卒業 |
| 和歌山県立医科大学臨床研修センター |
| 名古屋セントラル病院(旧JR東海病院)消化器内科 |
| 近畿大学病院 消化器内科医局 |
| 石川消化器内科内視鏡クリニック開院 |







