ピロリ菌感染の症状チェック〜早期発見のポイント
ピロリ菌感染症とは?〜基本知識と感染経路
ピロリ菌(ヘリコバクター・ピロリ)は、胃の粘膜に感染する細菌です。この菌は胃の中という強酸性の環境でも生存できる特殊な能力を持っています。私が日々の診療で多くの患者さんに説明しているのは、この菌が様々な胃の病気と深く関わっているという点です。
慢性胃炎の方のピロリ菌感染率はほぼ100%、胃潰瘍では70~90%、十二指腸潰瘍では90~95%がピロリ菌に感染しているとされています。胃がん患者の約99%以上にピロリ菌感染歴があるというデータもあります。
ピロリ菌の感染経路については、一般的に幼少期までに経口感染するとされています。主な感染経路は、ピロリ菌に感染している大人が使った箸を共有することによる家族内感染です。井戸水を使用する家庭が多かったこと、上下水道の整備が不十分であったことなどから、1970年以前に生まれた方は、それ以降に生まれた方と比べると、感染率が高いと言われています。
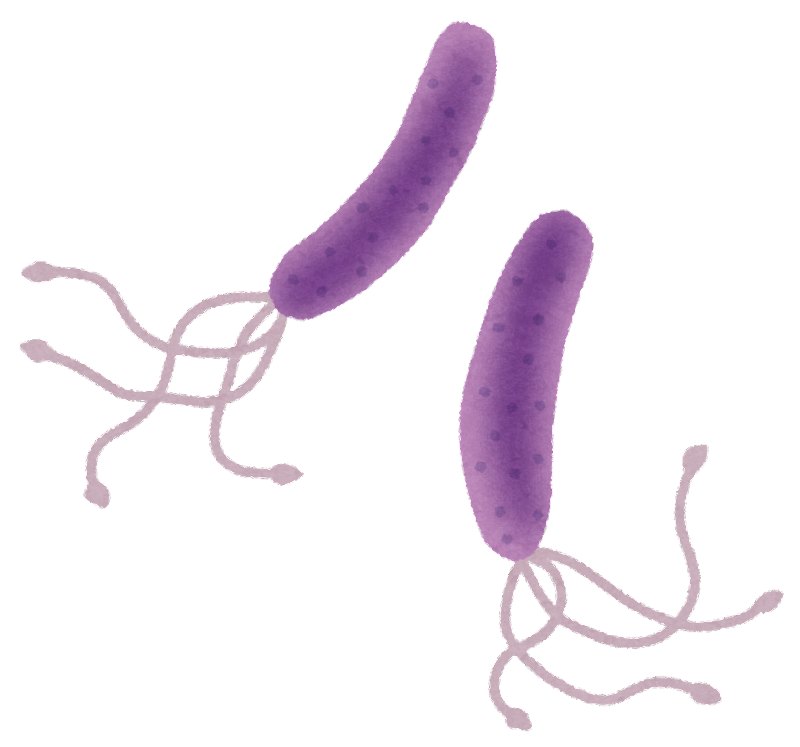
ピロリ菌感染の自己チェックポイント
ピロリ菌に感染していても、多くの場合は自覚症状がほとんどありません。しかし、以下のような症状や状況がある方は、ピロリ菌感染の可能性を考慮する必要があります。
まずは簡単なセルフチェックで、ご自身の状況を確認してみましょう。次の項目に当てはまるものがあれば、ピロリ菌検査を受けることをお勧めします。
- 胃の不快感が半年以上続いている
- 胃薬を飲んでも効果が一時的にしか続かない
- 健康診断のバリウム検査で異常を指摘された
- 井戸水を生活用水として使用していた時期がある
- 家族にピロリ菌に感染した方がいる
- 胃炎や胃・十二指腸潰瘍の既往歴がある
これらの項目に1つでも当てはまる方は、ピロリ菌検査を検討されることをお勧めします。特に複数項目に該当する場合は、感染の可能性が高いと考えられます。
ピロリ菌感染で引き起こされる主な症状と病気
ピロリ菌に感染しただけでは、すぐに症状は現れません。しかし、感染が長期間続くと、様々な病気の発症リスクが高まります。私の臨床経験からも、早期発見・早期治療が重要であることを日々実感しています。
ピロリ菌感染が原因で発症する主な病気と症状について解説します。
慢性胃炎
ピロリ菌は胃の粘膜に感染し、尿素をアンモニアに分解することで胃酸から身を守ります。このアンモニアが胃粘膜に悪影響を与え、長期間にわたると慢性胃炎を引き起こします。
慢性胃炎の主な症状には、胃もたれ、胃痛、吐き気、食欲不振などがあります。しかし、症状がないまま進行することも多く、定期的な検査が重要です。
胃潰瘍・十二指腸潰瘍
ピロリ菌が出す毒素により胃や十二指腸の粘膜の防御機能が低下します。これにより、胃酸や消化酵素から粘膜を守る機能が弱まり、胃潰瘍や十二指腸潰瘍が発生しやすくなります。
潰瘍の症状としては、空腹時や食後の胃の痛み、胸やけ、吐き気、嘔吐、黒色便(消化管出血の兆候)などが現れることがあります。
萎縮性胃炎
慢性胃炎が進行すると、胃液や胃酸を分泌する組織が減少し、胃の粘膜が萎縮して薄くなります。この状態を萎縮性胃炎と言います。
萎縮性胃炎になると、胃の機能は大きく低下し、胃液や胃酸が十分に分泌されなくなるため、食欲不振や胃もたれ、胸やけ、げっぷなどの症状が現れることがあります。また、胃がんのリスクも高くなります。
胃がん
長期間のピロリ菌感染によって胃粘膜の萎縮が進行すると、胃がんの発症リスクが高くなります。胃がん患者のほとんどがピロリ菌に感染しているというデータもあります。
胃がんの初期症状は非常に乏しく、進行するまで気づかないことも多いです。そのため、ピロリ菌感染者は定期的な胃カメラ検査が重要です。

ピロリ菌検査を受けるべき人
無症状であっても、以下に該当する人には、一度ピロリ菌検査を受けることをお勧めします。私の臨床経験からも、早期発見・早期治療が様々な胃の病気の予防に効果的であることを実感しています。
ピロリ菌感染症や胃がんの家族歴がある人
胃がん患者の99%がピロリ菌に感染していたというデータがあります。胃がん患者は、ほぼ確実にピロリ菌に感染していると言うことができます。
つまりピロリ菌感染症になったことがある・胃がんになったことがあるという人と幼少期に同居していた、特に親子関係であったという場合には、ピロリ菌に感染している可能性が高いと言えます。
胃カメラ検査やピロリ菌検査を受けたことがない30歳以上の人
身体も元気な20代、30代の方は、健康への心配をしていない人も多いかと思います。しかし、胃カメラ(内視鏡)検査やピロリ菌検査を一度も受けていないのであれば、一度検査を受けることをお勧めします。
若いうちにピロリ菌を除菌しておけば、将来的な胃がんのリスクをかなり下げることができます。また胃カメラを使ってピロリ菌検査を行う場合には、胃炎や胃潰瘍・十二指腸潰瘍、あるいは胃がんなどの早期発見・早期治療につながります。
除菌治療後に判定を受けていない人
ピロリ菌の除菌治療を受け、除菌に成功した人は、その後再度ピロリ菌に感染する可能性は極めて低いと考えられます。
しかし中には、ピロリ菌の除菌治療を受けたものの、その後の成否の判定を受けていないという方もいらっしゃいます。ピロリ菌の除菌治療の成功率は100%ではないため、未だピロリ菌に感染している可能性があります。
ピロリ菌の検査方法
ピロリ菌の検査方法は大きく分けて、胃カメラを使用する検査と使用しない検査があります。それぞれの特徴を理解して、自分に合った検査方法を選ぶことが大切です。
胃カメラを使用する検査
胃カメラで胃粘膜を一部採取し、感染の有無を判定します。この方法は直接胃の状態を確認できるため、胃炎や潰瘍、がんなどの早期発見にもつながります。
- 迅速ウレアーゼ試験:採取した組織を特殊な試薬に入れ、色の変化を見て感染の有無を判定する方法です。短時間で結果が出るのが特徴です。
- 培養法:採取した組織を培養して、ピロリ菌の有無を確認する方法です。正確な検査方法ですが、結果が出るまでに約1週間かかります。
- 鏡検法:採取した組織をホルマリンで固定し、顕微鏡でピロリ菌の有無を確認する方法です。
胃カメラを使用しない検査
ピロリ菌に感染しているかどうかは、尿や便を調べることで確認することもできます。これらの検査方法は簡便ですが、感度は培養法などに比べるとやや劣ります。
- 尿素呼気試験:診断薬を服用後に風船に息を吐き、呼気中の成分を調べることで胃の中に潜むピロリ菌の有無を確認し、感染の有無を判定します。
- 糞便中抗原測定:ピロリ菌は胃粘膜に感染しますが、菌の一部は落下して便に混ざります。そのため、便中にピロリ菌が存在するかどうかを確認して、感染の有無を判定します。
- 抗体測定(血液・尿):ピロリ菌に感染すると、抵抗力として菌に対する抗体をつくります。血液中や尿中などに存在するこの抗体の有無を調べる方法です。
それぞれの検査方法には長所と短所があります。胃カメラを使用する検査は直接胃の状態を確認できる利点がありますが、検査自体に抵抗感がある方もいらっしゃいます。一方、胃カメラを使用しない検査は比較的簡単に受けられますが、胃の状態を直接確認することはできません。

ピロリ菌の除菌治療
ピロリ菌が発見されたら、除菌治療を行うことが重要です。除菌することで、胃炎や胃潰瘍、胃がんなどのリスクを大幅に減らすことができます。
薬による治療
ピロリ菌の治療では、胃酸の分泌を抑える薬と2種類の抗菌薬の合計3剤を、1日に2回、7日間服用するのが一般的です。この治療法を一次除菌と呼びます。
一次除菌で成功しなかった場合は、抗菌薬の一つを別の種類に変更して再度治療を行います(二次除菌)。二次除菌でも成功しなかった場合は、さらに別の抗菌薬を使用した三次除菌を行うこともあります。
除菌治療の副作用
除菌治療中に、下痢、軟便、味覚異常、吐き気などの副作用が現れることがあります。これらの副作用は一般的に軽度で、治療終了後に自然に改善することがほとんどです。
ただし、重度の下痢や発熱、発疹などの症状が現れた場合は、薬剤アレルギーの可能性があるため、すぐに医師に相談してください。
除菌成功の判定
除菌治療終了後、4週間以上経過してから除菌成功の判定検査を行います。この期間は、抗菌薬の影響がなくなり、正確な判定ができるようになるまでの時間です。
判定検査には、尿素呼気試験や便中抗原検査などが用いられます。除菌が成功していれば、その後再感染する可能性は非常に低いとされています。
ピロリ菌感染予防と健康管理のポイント
ピロリ菌感染を予防し、胃の健康を維持するためのポイントをご紹介します。日々の生活習慣の改善と定期的な検査が重要です。
感染予防の基本
ピロリ菌は主に幼少期に感染するため、特に小さなお子さんがいるご家庭では以下の点に注意しましょう。
- 食器の共有を避ける:特に箸や食べかけの食べ物の口移しは避けましょう。
- 清潔な水の使用:安全な水道水や浄水器を通した水を使用しましょう。
- 手洗いの徹底:食事前や調理前の手洗いを徹底しましょう。
定期的な検査の重要性
ピロリ菌感染の有無にかかわらず、定期的な胃の検査は重要です。特に以下の方は定期的な検査をお勧めします。
- ピロリ菌陽性と診断された方:除菌治療を検討しましょう。
- 除菌治療を受けた方:除菌成功の判定検査を必ず受けましょう。
- ピロリ菌陰性の方:定期的な健康診断で胃の状態をチェックしましょう。
- 胃がんの家族歴がある方:より頻繁な検査が推奨されます。
生活習慣の改善
胃の健康を維持するためには、以下のような生活習慣の改善も重要です。
- バランスの良い食事:野菜や果物を多く摂り、塩分や刺激物の摂取を控えましょう。
- 禁煙:喫煙は胃粘膜を傷つけ、胃がんのリスクを高めます。
- 適度な飲酒:過度の飲酒は胃粘膜を刺激します。
- ストレス管理:ストレスは胃酸の過剰分泌を促し、胃の不調を引き起こします。
- 規則正しい食生活:食事の時間を規則的にし、早食いや過食を避けましょう。

まとめ:ピロリ菌感染症の早期発見と対策
ピロリ菌感染症は、早期発見・早期治療が非常に重要です。感染していても自覚症状がないことが多いため、リスク要因がある方は積極的に検査を受けることをお勧めします。
特に、胃の不快感が長期間続く、胃薬の効果が一時的、家族にピロリ菌感染者や胃がん患者がいるなどの場合は、ピロリ菌検査を検討しましょう。
検査方法には胃カメラを使用するものと使用しないものがあり、それぞれに特徴があります。胃カメラ検査では同時に胃の状態も確認できるため、より総合的な診断が可能です。
ピロリ菌が発見された場合は、適切な除菌治療を行うことで、胃炎、胃潰瘍、胃がんなどのリスクを大幅に減らすことができます。除菌治療後は必ず判定検査を受け、確実に除菌されたことを確認しましょう。
日常生活では、食器の共有を避ける、清潔な水を使用する、バランスの良い食事を心がけるなどの予防策も重要です。
胃の健康は全身の健康につながります。ピロリ菌感染の早期発見と適切な治療で、健やかな胃を維持しましょう。
ピロリ菌検査や胃カメラ検査をご希望の方は、お気軽に当院までご相談ください。あなたの胃の健康をサポートいたします。
大阪消化器内科・内視鏡クリニック難波院では、日本内視鏡学会認定の内視鏡専門医による胃カメラ検査・大腸カメラ検査を提供しています。鎮静剤を使用した苦痛の少ない検査で、ピロリ菌検査・除菌にも対応しております。詳しくは当院ウェブサイトをご覧ください。
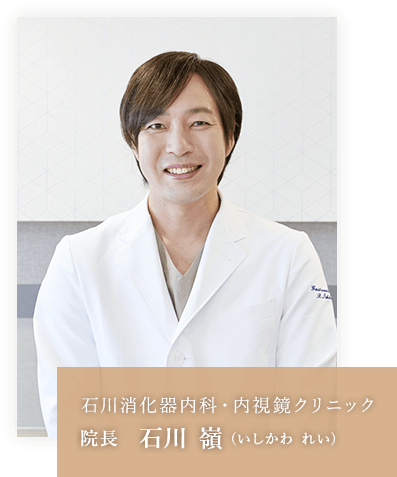
著者情報
理事長 石川 嶺
経歴
| 近畿大学医学部医学科卒業 |
| 和歌山県立医科大学臨床研修センター |
| 名古屋セントラル病院(旧JR東海病院)消化器内科 |
| 近畿大学病院 消化器内科医局 |
| 石川消化器内科内視鏡クリニック開院 |







