おならが多い原因と病気の可能性〜消化器内科医が解説
おならが多いと感じたら〜消化器内科医からの視点
おならは誰にでも出るものですが、急に回数が増えたり、臭いが強くなったりすると気になるものです。「最近おならが多いな」と感じることはありませんか?
おならは私たちの消化器系の健康状態を反映する重要なサインです。通常、健康な人は1日に7〜20回程度のおならを排出しています。これを超えて頻繁に出る場合は、何らかの原因があるかもしれません。
消化器内科医として日々多くの患者さんを診察していると、おならの悩みを抱える方は意外と多いことがわかります。特に「人前で出てしまうのが恥ずかしい」「臭いが強くて困っている」といった相談をよく受けます。
おならが増える原因は様々ですが、単なる食生活の問題から、過敏性腸症候群や大腸がんなどの病気まで、幅広い可能性があります。今回は消化器内科医の立場から、おならが多くなる原因と、注意すべき病気の可能性について詳しく解説していきます。
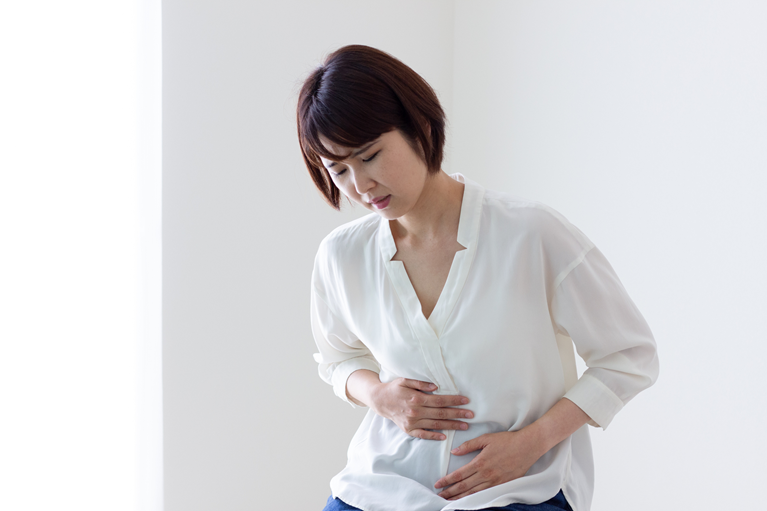
おならはどのようにして作られるのか
まず、おならがどのように体内で作られるのかを理解しましょう。おならの正体は腸内のガスです。
おならの約7割は、食事の際に一緒に飲み込んだ空気です。残りの3割は、腸内細菌の働きによって発生するガスや、血液から腸の粘膜を通って出てくるガスで構成されています。口から入った空気や血液から出てくるガスは基本的に無臭ですが、腸内細菌が作り出すガスには独特の臭いがあります。
食べ物の消化過程で、腸内細菌が食物繊維やオリゴ糖などを発酵させる際にガスが発生します。これが腸内を通過して肛門から排出されるのがおならです。健康な状態では、このガスの生成と排出のバランスが保たれています。
おならの臭いの主な原因は、腸内細菌が食物中のタンパク質や硫黄化合物を分解する過程で生じる硫化水素やメチルメルカプタンなどの物質です。肉類や卵、チーズなど硫黄を多く含む食品を摂取すると、これらの臭い成分が増加します。
私の臨床経験では、患者さんの多くが「おならが多い」と感じる基準は個人差がありますが、1日に25回以上のおならが出る場合は「多い」と考えられます。また、おならの量や臭いが急に変化した場合は、体内で何らかの変化が起きている可能性があります。
おならが多くなる一般的な原因
おならが増える原因は日常生活に関連するものが多いです。特に食生活の影響は大きいでしょう。
まず挙げられるのは、ガスを発生させやすい食品の摂取です。豆類、キャベツ、ブロッコリー、玉ねぎなどの食物繊維が豊富な野菜は、腸内細菌によって発酵されやすく、ガスを多く発生させます。これらは健康に良い食品ですが、一度に大量に摂取するとおならが増える原因になります。
炭酸飲料やビールなどの発泡性飲料も、おならを増やす原因となります。これらの飲み物に含まれる炭酸ガスが直接腸に届き、おならとして排出されるのです。また、早食いや会話しながらの食事は、無意識のうちに空気を多く飲み込んでしまう原因になります。
便秘もおならが増える重要な要因です。便が腸内に長く滞留すると、腸内細菌による発酵・腐敗が進み、ガスの発生量が増加します。さらに、このガスには有害物質も含まれており、一部は腸壁から吸収されて体調不良や肌荒れの原因にもなります。
ストレスや緊張も腸の動きに影響を与え、おならを増やすことがあります。ストレスによって腸の運動が乱れると、食物の消化・吸収に支障をきたし、ガスが多く発生するのです。
食生活とおならの関係
私の診察室でよく聞かれるのが「どんな食べ物を避ければおならが減りますか?」という質問です。実際、食事内容はおならの量や臭いに大きく影響します。
特に注意したいのは、肉類の食べ過ぎです。肉類に含まれるタンパク質は消化に時間がかかり、大腸まで到達する前に細菌によって分解されると、臭い成分が生成されます。にんにくなどの香味野菜に含まれる硫黄成分も、消化過程で臭いのあるガスを生成することがあります。
一方で、善玉菌のエサとなるオリゴ糖や食物繊維は、腸内環境を整える効果がありますが、急に摂取量を増やすとガスの発生も増えます。これらは徐々に量を増やしていくことで、腸が適応していきます。
乳糖不耐症の方は、牛乳や乳製品の摂取後におならが増えることがあります。これは腸内で乳糖を分解する酵素(ラクターゼ)が不足しているためで、特にアジア人に多く見られます。
生活習慣とおならの関係
食生活以外にも、様々な生活習慣がおならの量に影響します。
運動不足は腸の動きを鈍らせ、便秘やガスの滞留を引き起こします。適度な運動は腸の蠕動運動を促進し、ガスの排出をスムーズにする効果があります。特に散歩やヨガなどの軽い運動は、腸の働きを活性化させるのに効果的です。
また、姿勢も重要です。デスクワークなどで長時間同じ姿勢を続けると、腸が圧迫されてガスが滞留しやすくなります。定期的に立ち上がって軽く体を動かすことで、腸内のガスの流れを改善できます。
水分摂取も見逃せません。水分不足は便の硬化を招き、便秘の原因となります。1日に適切な量の水分(約1.5〜2リットル)を摂ることで、便通が改善し、おならの問題も軽減される場合があります。

おならの増加が示す可能性のある病気
おならの増加は単なる食生活の問題だけでなく、様々な消化器疾患のサインである可能性もあります。特に他の症状を伴う場合は注意が必要です。
過敏性腸症候群(IBS)は、おならの増加を引き起こす代表的な疾患です。腹痛や腹部不快感に加えて、便秘や下痢、またはその両方が繰り返し起こるのが特徴です。検査をしても器質的な異常が見つからないにもかかわらず、これらの症状が続く場合に診断されます。
IBSの患者さんでは、腸の運動や知覚機能に問題があり、正常な人よりも腸の動きが敏感になっています。ストレスや特定の食品によって症状が悪化することが多く、おならの増加もその一つです。
炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病)も、おならの増加を引き起こすことがあります。これらの疾患では腸の粘膜に炎症が生じ、腸内環境が乱れることでガスの発生が増えます。血便や持続的な下痢、体重減少などの症状を伴うことが多いのが特徴です。
腸内細菌のバランスが崩れる小腸内細菌過剰増殖症候群(SIBO)も、おならの増加の原因となります。通常、小腸には大腸ほど多くの細菌は存在しませんが、何らかの理由で小腸内に細菌が過剰に増殖すると、食物の発酵が早まり、ガスの発生が増加します。
注意すべき病気とその症状
おならの増加に加えて、以下のような症状がある場合は、早めに医療機関を受診することをお勧めします。
大腸がんは、初期段階ではほとんど症状が現れないことが多いですが、進行すると便通の変化やおならの増加、血便などの症状が現れることがあります。特に50歳以上の方で、これらの症状が続く場合は注意が必要です。
セリアック病(グルテン不耐症)も、おならの増加を引き起こすことがあります。小麦、大麦、ライ麦などに含まれるグルテンに対する免疫反応によって小腸が損傷し、消化吸収障害が生じます。下痢、腹痛、体重減少などの症状を伴うことが多いです。
乳糖不耐症は、牛乳や乳製品に含まれる乳糖を分解する酵素の不足によって起こります。乳製品の摂取後に腹部膨満感、おならの増加、下痢などの症状が現れるのが特徴です。
胆嚢疾患や膵臓疾患も、消化プロセスに影響を与えることでおならの増加を引き起こすことがあります。特に脂っこい食事の後に症状が悪化する傾向があります。
大腸がんとおならの関係
特に注意が必要なのが大腸がんとおならの関係です。大腸がんは日本人のがん死亡原因の上位を占める重要な疾患です。
大腸がんが進行すると、腫瘍が腸管を狭窄させることで腸内容物の通過が妨げられ、結果としておならの性状や頻度に変化が生じることがあります。また、腫瘍周囲での細菌叢の変化によって、おならの臭いが変わることもあります。
私の臨床経験からも、「最近おならの臭いが変わった」「便の形状が細くなった」といった症状を訴えて来院し、検査の結果、大腸がんが見つかるケースがあります。
おならの増加だけでなく、以下のような症状が併せて現れる場合は、大腸がんの可能性を考慮して早めに消化器内科を受診することをお勧めします。
- 血便や黒色便
- 便通の習慣の変化(便秘と下痢の繰り返しなど)
- 腹痛や腹部不快感
- 原因不明の体重減少
- 貧血
大腸がんは早期発見・早期治療が可能な疾患です。定期的な大腸がん検診を受けることで、症状が現れる前に発見できる可能性が高まります。

おならが多い時の対処法と生活改善
おならが多くて悩んでいる方に、まず試していただきたいのが生活習慣の改善です。多くの場合、簡単な対策で症状が改善することがあります。
食事の改善は最も効果的なアプローチの一つです。ガスを発生させやすい食品(豆類、キャベツ、ブロッコリー、玉ねぎなど)の摂取量を一時的に減らしてみましょう。ただし、これらは栄養価の高い食品なので、完全に避けるのではなく、量を調整することが大切です。
食事のペースも重要です。ゆっくりと時間をかけて食べることで、空気を飲み込む量が減り、おならの発生も抑えられます。また、炭酸飲料やビールなどの発泡性飲料の摂取を控えることも効果的です。
便秘の改善もおならの減少につながります。食物繊維の適切な摂取、十分な水分補給、規則正しい排便習慣の確立が重要です。特に朝食後にトイレに行く習慣をつけると、胃結腸反射を利用した自然な排便が促されます。
ストレス管理も見逃せません。ストレスは腸の動きに大きく影響します。深呼吸、瞑想、軽い運動などでストレスを軽減することで、腸の機能も改善することがあります。
おならを減らす食事のポイント
おならを減らすための食事療法について、もう少し詳しく見ていきましょう。
低FODMAP食は、過敏性腸症候群の患者さんにしばしば推奨される食事法です。FODMAPとは発酵性オリゴ糖、二糖類、単糖類、ポリオールの総称で、これらは腸内で発酵されやすく、ガスを多く発生させる成分です。
低FODMAP食では、以下のような食品を一時的に制限します:
- フルクタンを含む食品(小麦、玉ねぎ、にんにくなど)
- 乳糖を含む食品(牛乳、ソフトチーズなど)
- フルクトースを多く含む食品(りんご、梨、はちみつなど)
- ポリオールを含む食品(桃、プラム、人工甘味料など)
- ガラクタンを含む食品(豆類、レンズ豆など)
ただし、これらの食品を完全に排除するのではなく、症状が改善した後に少しずつ再導入していくのが一般的です。また、個人によって反応する食品は異なるため、食事日記をつけて自分に合った食事法を見つけることが大切です。
発酵食品(ヨーグルト、キムチ、漬物など)は、腸内細菌のバランスを整える効果が期待できますが、人によっては一時的にガスが増えることもあります。少量から始めて、徐々に量を増やしていくとよいでしょう。
医療機関を受診すべきタイミング
生活習慣の改善を試みても症状が改善しない場合や、以下のような症状がある場合は、早めに消化器内科を受診することをお勧めします。
血便や黒色便がある場合は、消化管からの出血を示している可能性があり、早急な医療評価が必要です。持続的な腹痛、特に夜間に悪化する痛みや、食事と関係なく現れる痛みも注意が必要です。
原因不明の体重減少や食欲不振、倦怠感などの全身症状を伴う場合も、何らかの疾患が隠れている可能性があります。また、おならの性状(臭い、頻度など)が急激に変化した場合も、腸内環境の変化を示唆している可能性があります。
50歳以上の方で、これまでになかったおならの増加や便通の変化がある場合は、大腸がんのスクリーニング検査を検討する良い機会かもしれません。
医療機関では、症状の詳細な聴取に加えて、必要に応じて血液検査、便検査、腹部超音波検査、CT検査、内視鏡検査などが行われます。特に大腸内視鏡検査は、大腸の状態を直接観察できる重要な検査です。
私の診療では、患者さんの症状や年齢、リスク因子などを考慮して、適切な検査を提案しています。おならの増加だけでなく、全体的な健康状態を評価することが重要です。
まとめ〜おならの悩みを解消するために
おならは自然な生理現象ですが、急に増えたり、臭いが強くなったりすると、日常生活に支障をきたすことがあります。今回の記事では、おならが多くなる原因と、注意すべき病気の可能性について解説しました。
おならの増加は、食生活や生活習慣の問題から、過敏性腸症候群や大腸がんなどの疾患まで、様々な原因が考えられます。多くの場合、食事の見直しや生活習慣の改善で症状は軽減しますが、他の気になる症状を伴う場合や、改善が見られない場合は、専門医への相談をお勧めします。
特に血便、持続的な腹痛、原因不明の体重減少などの症状がある場合は、早めに消化器内科を受診してください。大腸がんなどの重大な疾患が隠れている可能性もあります。
おならの問題は恥ずかしくて相談しづらいかもしれませんが、消化器内科医にとっては日常的な相談内容です。遠慮なく専門医に相談することで、適切な診断と治療を受けることができます。
最後に、おならの増加だけでなく、便通の変化や腹部の不快感など、消化器系の症状に気づいたら、自己判断せずに医療機関を受診することをお勧めします。早期発見・早期治療が、健康維持の鍵となります。
おならの悩みを抱えている方は、ぜひ一度、消化器内科の専門医に相談してみてください。適切な診断と治療によって、快適な日常生活を取り戻すお手伝いをさせていただきます。
詳しい検査や治療についてのご相談は、大阪消化器内科・内視鏡クリニック難波院までお気軽にお問い合わせください。鎮静剤を使用した苦痛の少ない内視鏡検査や、最新の医療機器を用いた精密検査を提供しております。
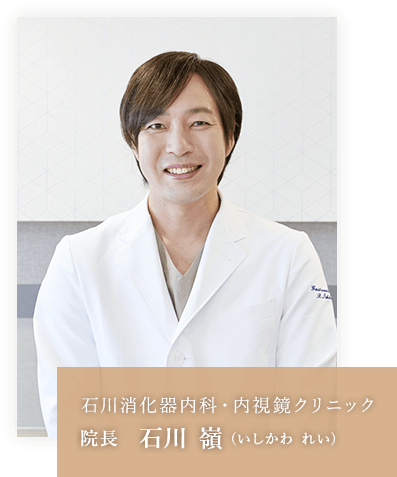
著者情報
理事長 石川 嶺
経歴
| 近畿大学医学部医学科卒業 |
| 和歌山県立医科大学臨床研修センター |
| 名古屋セントラル病院(旧JR東海病院)消化器内科 |
| 近畿大学病院 消化器内科医局 |
| 石川消化器内科内視鏡クリニック開院 |







