下痢が続く場合の受診目安〜専門医が教える判断基準
下痢が続くときの不安と受診の判断
突然の下痢は誰にでも起こりうる症状です。多くの場合は一時的なものですが、長く続く下痢は体調不良のサインかもしれません。患者さんからよく「どのくらい下痢が続いたら病院に行くべきですか?」という質問を受けます。
下痢が続くと日常生活に支障をきたすだけでなく、脱水症状を引き起こすリスクもあります。特に高齢者や小さなお子さんは注意が必要です。
私は消化器内科医として、下痢の症状に悩む多くの患者さんを診てきました。下痢が続く場合、いつ医療機関を受診すべきか、その判断基準を明確にすることは非常に重要です。この記事では、下痢が続く場合の受診目安について、専門医の立場から詳しくお伝えします。

下痢の定義と種類を理解する
まず、医学的な「下痢」の定義を理解しておきましょう。下痢とは「便形状が軟便あるいは水様便、かつ排便回数が増加する状態」と定義されます。排便回数の増加は一般的に3回/日以上とされていますが、個人の通常の排便習慣からの変化も重要な判断材料です。
下痢はその持続期間によって、急性と慢性に分けられます。急性下痢は突然発症し、通常は数日から1週間程度で改善します。一方、慢性下痢は4週間以上持続または反復する下痢と定義されています。
下痢の原因はさまざまで、感染症、食中毒、薬剤の副作用、ストレス、過敏性腸症候群、炎症性腸疾患など多岐にわたります。原因によって症状の現れ方や持続期間、随伴症状も異なるため、適切な診断と治療が必要です。
下痢の種類を理解することは、受診の判断に役立ちます。例えば、感染性の下痢は他の家族にも同様の症状が現れることがありますが、機能性の下痢は個人に限定されることが多いです。
下痢が続く場合の受診目安
下痢が続く場合、どのような状況で医療機関を受診すべきでしょうか。以下に、受診を検討すべき目安をご紹介します。
すぐに受診すべき緊急症状
下痢に加えて以下のような症状がある場合は、緊急性が高いため、すぐに医療機関を受診してください。
- 高熱(38℃以上)を伴う
- 血便や黒色便がある
- 激しい腹痛がある
- 嘔吐を繰り返す
- めまいや立ちくらみがある
- 強い脱水症状(口の渇き、尿量減少、皮膚の乾燥など)
- 意識がもうろうとする
特に高齢者や基礎疾患をお持ちの方、免疫機能が低下している方は、症状が急速に悪化する可能性があるため、早めの受診をお勧めします。
数日様子を見ても良い場合
一方、以下のような場合は、まず数日間様子を見ても良いでしょう。
- 発熱がない、または微熱程度
- 腹痛が軽度である
- 血便がない
- 水分摂取が十分できている
- 日常生活に大きな支障がない
ただし、症状が改善せず長引く場合や、徐々に悪化する場合は受診をお勧めします。特に、1週間以上下痢が続く場合は、慢性的な問題の可能性があるため、医療機関での評価が必要です。
慢性下痢症の受診目安
4週間以上続く下痢は「慢性下痢症」と呼ばれ、専門的な診断と治療が必要になることが多いです。慢性下痢症の場合、以下のような「警告症状・徴候」がある場合は、早めに消化器内科を受診することをお勧めします。
- 予期せぬ体重減少
- 夜間の下痢
- 最近の抗菌薬の服用歴
- 血便
- 大量・頻回の下痢
- 低栄養状態
- 炎症性腸疾患や大腸癌などの家族歴
これらの症状は、単なる機能性の問題ではなく、炎症性腸疾患や悪性疾患などの器質的疾患の可能性を示唆することがあります。
慢性下痢症の診断には、詳細な問診、血液検査、便検査、内視鏡検査などが必要になることがあります。特に、「便通異常症診療ガイドライン2023―慢性下痢症」では、慢性下痢症に対する大腸内視鏡検査は器質的疾患との鑑別診断・除外診断において有用であるため推奨されています。
慢性下痢症の患者さんのうち、17〜28%で内視鏡検査あるいはランダム生検で異常所見を認めるという報告があります。特に下痢型過敏性腸症候群との鑑別において、経験的治療で効果がない場合、警告徴候を有する場合、50歳以上では内視鏡検査を行うことが推奨されています。

年齢別の下痢症状と受診目安
下痢症状の重症度や受診の緊急性は、年齢によっても異なります。ここでは、年齢別の特徴と受診目安について解説します。
乳幼児・小児の場合
乳幼児や小児は、体内の水分量が少なく、脱水症状に陥りやすいため特に注意が必要です。以下のような場合は、早めに小児科を受診しましょう。
- 生後3ヶ月未満の乳児で38℃以上の発熱を伴う下痢
- 12時間以上下痢が何度も続いている
- 12時間以上おしっこが出ていない
- 口唇や舌が乾いている
- 元気がない、ぐったりしている
- 泣いても涙が出ない
- 皮膚の弾力性が低下している
特に、生後3ヶ月未満の赤ちゃんの発熱の約1割は、敗血症や細菌性髄膜炎などの深刻な感染症にかかっている恐れがあります。免疫機能が発達過程にある乳幼児は重症化しやすいため、注意が必要です。
成人の場合
成人の場合、以下のような症状がある場合は医療機関を受診しましょう。
- 3日以上続く下痢
- 高熱(38℃以上)を伴う
- 強い腹痛がある
- 血便がある
- 脱水症状(めまい、口の渇き、尿量減少など)
- 2週間以内の海外渡航歴がある
特に、血便を伴う下痢は、感染性腸炎や炎症性腸疾患、大腸ポリープ、大腸がんなどの可能性があるため、必ず医療機関を受診してください。
高齢者の場合
高齢者は脱水症状に陥りやすく、また基礎疾患を持っていることも多いため、下痢症状に対してより慎重な対応が必要です。以下のような場合は早めに受診しましょう。
- 2日以上続く下痢
- 発熱を伴う
- 腹痛がある
- 血便がある
- 脱水症状(めまい、口の渇き、尿量減少など)
- 服用中の薬がある(特に抗生物質、降圧剤、利尿剤など)
高齢者は症状が軽くても重篤な疾患が隠れていることがあります。また、脱水症状が進行すると腎機能障害や電解質異常を引き起こすリスクが高まるため、早めの受診が望ましいです。
下痢が続く場合の自宅でのケア方法
医療機関を受診するまでの間、または軽度の下痢の場合は、以下のような自宅でのケアを行うことで症状の緩和が期待できます。
水分・電解質の補給
下痢による脱水を防ぐため、こまめな水分補給が重要です。水だけでなく、電解質(ナトリウム、カリウムなど)も失われるため、経口補水液の利用がおすすめです。市販の経口補水液のほか、以下の方法で簡易的な経口補水液を作ることもできます。
- 水1リットルに対して、塩小さじ1/2(3g)と砂糖大さじ4〜6(40〜60g)を溶かす
- レモンやオレンジジュースを少量加えると飲みやすくなる
水分は一度に大量に飲むのではなく、少量ずつこまめに摂取することが大切です。特に子どもや高齢者は脱水症状に注意し、十分な水分補給を心がけましょう。
食事の工夫
下痢の際の食事は、消化に負担をかけない食品を選ぶことが大切です。
- 消化のよい食品(おかゆ、うどん、じゃがいも、白身魚など)
- バナナ、りんご(すりおろし)、トーストなどの軽い食事
- 脂肪分の多い食品、香辛料の強い食品、乳製品、アルコール、カフェインは避ける
症状が落ち着いてきたら、徐々に通常の食事に戻していきましょう。ただし、食欲がない場合は無理に食べる必要はなく、水分と電解質の補給を優先してください。
休息と生活習慣
下痢の回復には十分な休息も重要です。無理をせず、体を休めることで回復を早めることができます。また、手洗いの徹底など、衛生管理にも気を配りましょう。特に感染性の下痢の場合は、家族への感染予防のためにも重要です。
下痢が続く場合でも、市販の下痢止め薬の使用は慎重に検討してください。特に発熱や血便を伴う場合は、感染性の下痢の可能性があり、下痢止め薬によって病原体の排出が遅れる可能性があります。

専門医が行う下痢の検査と診断
医療機関を受診した場合、どのような検査や診断が行われるのでしょうか。ここでは、専門医が行う一般的な検査と診断プロセスについて解説します。
問診と身体診察
まず、詳細な問診と身体診察が行われます。下痢の持続期間、頻度、性状(水様、粘液性、血便など)、随伴症状(発熱、腹痛、嘔吐など)、最近の食事内容、服用中の薬剤、渡航歴などについて詳しく聞かれます。
身体診察では、腹部の触診や聴診、脱水症状の有無、全身状態などが評価されます。これらの情報から、緊急性の高い疾患の可能性や、必要な検査の種類が判断されます。
検査の種類
下痢の原因や重症度に応じて、以下のような検査が行われることがあります。
- 血液検査:炎症反応、電解質バランス、肝機能、腎機能などの評価
- 便検査:便培養検査、便中白血球、寄生虫検査、Clostridium difficile毒素検査など
- 画像検査:腹部エコー、CT検査など
- 内視鏡検査:大腸内視鏡検査、上部消化管内視鏡検査
特に慢性下痢症の場合、内視鏡検査が重要な役割を果たします。内視鏡検査では、消化管の粘膜の状態を直接観察でき、必要に応じて組織検査(生検)も行うことができます。
当院では、日本内視鏡学会認定の内視鏡専門医による胃カメラ検査・大腸カメラ検査を提供しています。鎮静剤(麻酔)を使用した苦痛の少ない検査を心がけており、患者さんの負担を最小限に抑えています。
まとめ:下痢が続く場合の受診判断
下痢が続く場合の受診目安について、ポイントをまとめます。
- 緊急受診が必要な場合:高熱、血便、激しい腹痛、嘔吐の繰り返し、脱水症状、意識障害など
- 数日様子を見ても良い場合:発熱がない、腹痛が軽度、血便がない、水分摂取が十分できている
- 慢性下痢(4週間以上)の場合:体重減少、夜間の下痢、血便、大量・頻回の下痢などの警告症状があれば受診を
- 年齢による注意点:乳幼児・高齢者は脱水症状に注意し、早めの受診を検討
下痢は多くの場合、数日で自然に改善しますが、上記のような警告症状がある場合や、症状が長引く場合は、専門医の診察を受けることをお勧めします。特に慢性的な下痢症状は、生活の質を大きく低下させるだけでなく、重大な疾患が隠れている可能性もあります。
当院では、消化器症状でお悩みの方に対して、丁寧な診察と必要に応じた検査を行い、適切な治療をご提案しています。下痢でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
健康な腸は健康な体の基本です。日頃からバランスの良い食事、適度な運動、十分な睡眠、ストレス管理などを心がけ、腸内環境を整えることも大切です。
下痢の症状でお悩みの方は、ぜひ一度専門医にご相談ください。
大阪消化器内科・内視鏡クリニック難波院では、消化器症状でお悩みの方に対して、専門的な診療を提供しています。詳しくは公式サイトをご覧ください。
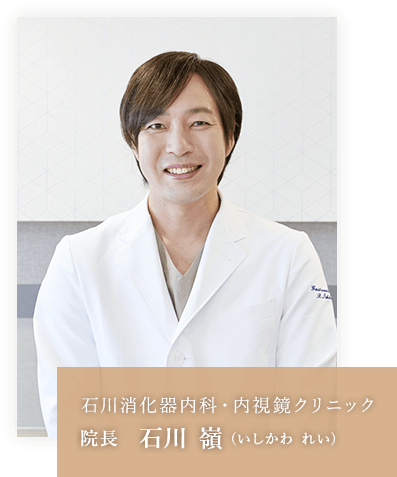
著者情報
理事長 石川 嶺
経歴
| 近畿大学医学部医学科卒業 |
| 和歌山県立医科大学臨床研修センター |
| 名古屋セントラル病院(旧JR東海病院)消化器内科 |
| 近畿大学病院 消化器内科医局 |
| 石川消化器内科内視鏡クリニック開院 |







