粉瘤は放置しても大丈夫?専門医が教える正しい対処法
粉瘤とは?症状と特徴を理解しよう
皮膚の下にできる「しこり」に気づいて、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。特に「粉瘤(ふんりゅう)」は、日常診療でもよく遭遇する皮膚の良性腫瘍です。
粉瘤は、皮膚からはがれ落ちる垢(角質)や皮脂が、皮膚の内側にある袋状の構造物にたまってできた腫瘍(嚢腫)の総称です。医学的には「表皮嚢腫」とも呼ばれています。
年齢や性別に関係なく誰にでも発症する可能性があり、身体のどの部位にもできる可能性がありますが、特に顔や首、背中などに発生しやすい傾向があります。数ミリから数センチ大のやや盛り上がったしこりとして触知でき、中央に黒点状の開口部(毛孔開口部、いわゆる「へそ」)が見られることが特徴的です。
強く押すと、白色〜黄色のドロドロとした内容物が出てくることがあります。この内容物は角質や皮脂が主成分で、独特の臭いを伴うことも特徴です。
粉瘤自体は基本的に良性の腫瘍であり、がんなどの悪性腫瘍とは異なります。しかし、放置すると様々な問題が生じる可能性があるため、適切な対処が必要です。

粉瘤を放置するとどうなるのか?
「小さな粉瘤だから放置しても大丈夫だろう」と考える方も多いかもしれません。しかし、粉瘤を放置するとどのような経過をたどるのでしょうか?
粉瘤は自然に治癒することはほとんどなく、放置すると以下のような状態になる可能性があります。
徐々に大きくなる
粉瘤の中身である角質や皮脂は袋の外に自然には排出されないため、放置すると少しずつ大きくなっていきます。小さなものでも時間をかけて成長し、野球ボール大になることもあります。
大きくなった粉瘤は見た目の問題だけでなく、周囲の組織を圧迫することで痛みや不快感を引き起こすこともあります。特に肩や背中など、衣服や日常動作による刺激を受けやすい部位では、不快感が増す傾向にあります。
炎症を起こす可能性
粉瘤に炎症が生じると、表面が赤くなり、痛みを伴うようになります。これが「炎症性粉瘤」です。
炎症が進行すると、赤みが拡大し、痛みも強くなります。袋の内容物が膿(うみ)となり、触るとブヨブヨとした感触になることもあります。腫れが限界に達すると、粉瘤が破裂して臭いドロドロの内容物が排出されることもあります。
さらに厄介なのが細菌感染の合併です。細菌感染により炎症症状は悪化し、強い痛みや腫れが生じると、緊急の切開処置が必要になることもあります。
まれに悪性化することがある
粉瘤は基本的に良性腫瘍ですが、非常にまれなケースとして、経過が非常に長く、大きかったり、炎症を繰り返したりした場合に悪性化することがあります。
特に注意が必要なのは、中高年の男性の頭部、顔面、臀部にできた大きな粉瘤で、急速に大きくなったり、表面の皮膚に傷ができたりする場合です。
悪性化を防ぐためにも、小さなうちの早めの手術をおすすめします。
粉瘤はなぜできるのか?原因を探る
粉瘤の発生原因は多くの場合不明ですが、いくつかの要因が関連していると考えられています。
外傷や刺激による発生
打撲や外傷などの後に粉瘤が発生することがあります。皮膚が損傷を受けることで、表皮細胞が真皮内に埋め込まれ、そこで増殖して嚢胞を形成すると考えられています。
ピアスの穴も粉瘤の原因となることがあります。繰り返しピアスを刺すことで、皮膚の表皮成分が真皮層に移植され、成分が蓄積されて粉瘤が形成されることがあります。
ニキビ痕との関連
ニキビの跡に粉瘤ができることもあります。ニキビによる炎症で毛包が閉塞し、皮脂の排出が妨げられることで粉瘤が形成される可能性があります。
特に背中や胸など、ニキビができやすい部位では、粉瘤も発生しやすい傾向があります。
ウイルス感染との関連
イボウイルス(ヒトパピローマウイルス)などの感染が関与している可能性も指摘されています。ウイルスが皮膚細胞に感染することで、細胞の増殖パターンが変化し、粉瘤の形成につながる場合があります。
ただし、粉瘤は不潔にしているためにできるわけではありません。清潔にしていても発生することがあるため、過度に心配する必要はありません。
残念ながら、現時点では粉瘤の発生を確実に予防する方法はなく、できてしまった場合は適切な治療を受けることが重要です。
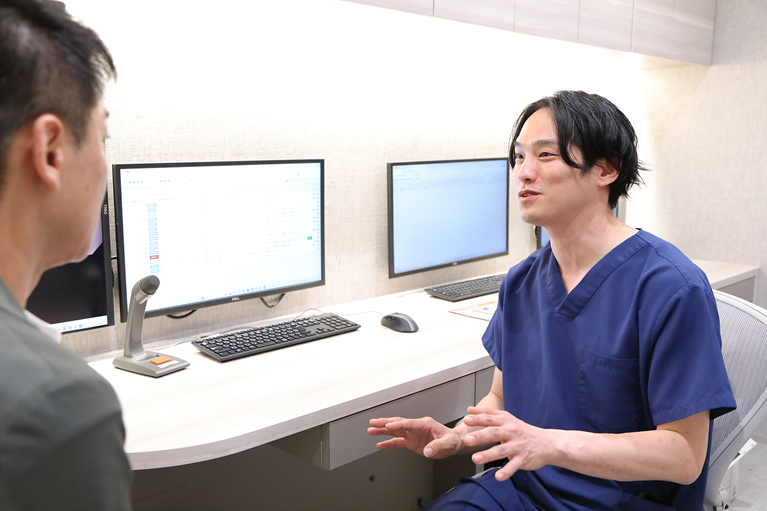
粉瘤の適切な治療法とは?
粉瘤の治療法は、その大きさや状態、発生部位によって異なります。ここでは、主な治療法について解説します。
切開排膿(炎症時の応急処置)
炎症を起こして膿がたまってしまった炎症性粉瘤に対しては、まず切開排膿を行います。これは皮膚を切開して、たまっている膿を排出する処置です。
炎症が強く膿がたまった状態では、膿を物理的に取り除かない限り炎症の改善が見込めません。局所麻酔で行いますが、切開部分は縫わずに開放したままにするのが一般的です。
切開排膿はあくまで応急処置であり、炎症が落ち着いた後に改めて粉瘤の摘出手術を行うことが一般的です。そのため、炎症のない状態での手術に比べて治療期間が長くなります。
なお、切開排膿後は翌日に切開部分の確認、さらに1週間後に処置のための来院が必要です。
くりぬき法
「くりぬき法」は、粉瘤の中央にある黒点状の開口部(へそ)を中心に小さな切開を加え、内容物を排出した後、嚢胞壁(袋)を摘出する方法です。
この方法のメリットは、比較的小さな切開で済むため、傷跡が目立ちにくいことです。また、手術時間も短く、日帰りで行えます。
ただし、すべての粉瘤に適用できるわけではなく、小さめの粉瘤や、炎症や癒着のない粉瘤に適しています。また、嚢胞壁が完全に摘出できないと再発のリスクが高まるというデメリットもあります。
メスによる切除縫合
「メスによる切除縫合」は、粉瘤の上の皮膚を切開し、嚢胞壁ごと完全に摘出した後、傷口を縫合する方法です。
この方法は、大きな粉瘤や炎症を繰り返している粉瘤、癒着のある粉瘤に適しています。嚢胞壁を完全に摘出できるため、再発のリスクが低いというメリットがあります。
ただし、くりぬき法に比べて切開が大きくなるため、傷跡が残りやすいというデメリットがあります。また、手術時間も比較的長くなります。
どちらの手術方法も保険診療で受けることができます。粉瘤の状態や部位、患者さんの希望などを考慮して、最適な治療法を選択することが重要です。

粉瘤の手術後の経過と注意点
粉瘤の手術を受けた後は、適切なケアと注意が必要です。手術後の経過と注意点について解説します。
手術直後から数日間の注意点
手術直後は、傷口を清潔に保つことが最も重要です。医師の指示に従って、適切な頻度で消毒や包帯の交換を行いましょう。
また、手術部位の安静も重要です。特に運動や入浴については、医師の指示に従ってください。一般的には、手術後24〜48時間は入浴を控え、シャワーのみにすることが多いです。
痛みがある場合は、処方された鎮痛薬を用法・用量を守って服用してください。痛みが強くなる、出血が止まらない、発熱するなどの異常がある場合は、すぐに医師に相談しましょう。
長期的な経過観察
粉瘤の手術後は、再発の可能性もあるため、定期的な経過観察が重要です。特に、くりぬき法で手術を受けた場合は、嚢胞壁が完全に摘出できていない可能性があるため、注意が必要です。
手術部位に硬結(しこり)や腫れが再び現れた場合は、再発の可能性があります。気になる症状があれば、早めに医師に相談しましょう。
傷跡のケア
手術後の傷跡は、時間とともに薄くなっていきますが、完全に消えることはありません。傷跡を目立たなくするためには、以下のポイントに注意しましょう。
まず、傷が完全に治癒するまでは直射日光を避けることが重要です。紫外線は傷跡を濃くする原因になります。外出時は、傷跡を覆う服を着たり、日焼け止めを塗ったりするなどの対策をしましょう。
また、医師の指示があれば、傷跡用のクリームやシリコンシートを使用することも効果的です。ただし、自己判断で使用せず、必ず医師に相談してから使用してください。
粉瘤に関するよくある質問
粉瘤について患者さんからよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
粉瘤は自然に治ることがありますか?
粉瘤が自然に治ることは非常にまれです。多くの場合、放置すると徐々に大きくなったり、炎症を起こしたりする可能性があります。小さなうちに適切な治療を受けることをおすすめします。
中には内容物が自然に排出されて一時的に小さくなることもありますが、嚢胞壁(袋)が残っている限り再発する可能性が高いです。
粉瘤の手術は痛いですか?
手術時は局所麻酔を使用するため、麻酔が効いている間は痛みをほとんど感じません。麻酔の注射時に一時的な痛みがありますが、すぐに和らぎます。
手術後は、麻酔が切れてくると多少の痛みや不快感を感じることがありますが、処方された鎮痛薬で対処できる程度です。炎症を起こしている場合は、手術後の痛みが強くなることがあります。
粉瘤の手術後、仕事や日常生活はいつから再開できますか?
手術の範囲や部位によって異なりますが、多くの場合、軽作業であれば手術当日または翌日から再開できます。ただし、手術部位に負担がかかる作業や激しい運動は、1〜2週間程度控えることが望ましいでしょう。
入浴については、医師の指示に従ってください。一般的には、手術後24〜48時間は入浴を控え、シャワーのみにすることが多いです。
粉瘤の手術は保険が適用されますか?
粉瘤の手術は、基本的に保険適用となります。ただし、美容目的と判断された場合は、保険適用外となる可能性があります。
保険適用の場合、3割負担で数千円〜1万円程度の自己負担額となることが多いですが、粉瘤の大きさや部位、手術方法によって異なります。詳細は医療機関にお問い合わせください。

専門医が教える粉瘤との付き合い方
消化器内科・内視鏡専門医の立場から、粉瘤との適切な付き合い方についてアドバイスします。
早期発見・早期治療の重要性
粉瘤は小さいうちに治療するのが最も簡単で、傷跡も最小限に抑えられます。気になるしこりを見つけたら、早めに皮膚科や外科を受診しましょう。
特に、急に大きくなったり、痛みや赤みを伴ったりする場合は、炎症や感染の可能性があるため、すぐに医療機関を受診することが重要です。
自己判断での処置は危険
インターネットなどで「自分で粉瘤を潰す方法」などの情報を見かけることがありますが、素人が自己判断で粉瘤を潰すことは非常に危険です。
不適切な処置は感染を引き起こしたり、嚢胞壁が完全に取り除かれずに再発したりする原因になります。必ず医療機関で適切な治療を受けてください。
定期的な皮膚チェックの習慣づけ
粉瘤に限らず、皮膚の異常を早期に発見するためには、定期的な皮膚チェックが重要です。入浴時などに全身の皮膚をチェックする習慣をつけましょう。
特に、以前に粉瘤ができたことがある方は、再発や新たな粉瘤の発生に注意が必要です。気になる変化があれば、早めに医療機関を受診しましょう。
まとめ:粉瘤は放置せず適切な治療を
粉瘤は良性の腫瘍ですが、放置すると徐々に大きくなったり、炎症を起こしたりする可能性があります。まれに悪性化することもあるため、早期の適切な治療が重要です。
粉瘤の治療法には、くりぬき法やメスによる切除縫合などがあり、粉瘤の状態や部位によって最適な方法が選択されます。どちらも保険適用で受けることができます。
手術後は、傷口を清潔に保ち、医師の指示に従って適切なケアを行うことが大切です。また、再発の可能性もあるため、定期的な経過観察も重要です。
皮膚に気になるしこりを見つけたら、自己判断での処置は避け、早めに医療機関を受診しましょう。専門医による適切な診断と治療を受けることが、粉瘤との付き合い方の基本です。
当院では、皮膚のできものを含む様々な症状に対応しております。気になる症状がございましたら、お気軽に石川消化器内科・内視鏡クリニックまでご相談ください。

著者情報
理事長 石川 嶺
経歴
| 近畿大学医学部医学科卒業 |
| 和歌山県立医科大学臨床研修センター |
| 名古屋セントラル病院(旧JR東海病院)消化器内科 |
| 近畿大学病院 消化器内科医局 |
| 石川消化器内科内視鏡クリニック開院 |







