切れ痔は放置しても治る?自然治癒の条件と適切な対処法
切れ痔とは?その症状と原因を理解しよう
切れ痔(裂肛)は、肛門の出口付近の皮膚が切れている状態です。排便時に痛みを感じ、排便後もしばらく痛みが続くことがあります。出血の色は鮮やかな赤色で、出血量もトイレットペーパーや便につく程度と少ないのが特徴です。
痔の中でも、切れ痔は女性に多く見られます。便秘になりやすい女性は、硬い便が肛門を通過する際に皮膚を傷つけてしまうことが原因です。
切れ痔は、以下のように分類されます。
- 急性裂肛:硬い便により肛門の皮膚が限界以上に伸ばされて裂けてしまう傷
- 慢性裂肛:潰瘍状の深い傷ができ、ポリープやイボができることもある
- 脱出性裂肛:痔核(いぼ痔)や肛門ポリープが繰り返し脱出するとき、肛門の皮膚が引っ張られてできる傷
- 症候性裂肛:クローン病などの全身性疾患の部分症状として、肛門に切れ痔ができる状態
切れ痔の主な原因は、便の状態と排便習慣にあります。硬すぎる便や下痢による刺激、不適切な肛門の洗浄方法なども影響します。

切れ痔は放置しても自然治癒する?その条件と限界
「切れ痔になったけど、病院に行くのは恥ずかしい…」
多くの方がこう感じて、自然治癒を期待して放置することがあります。結論から言うと、急性裂肛の場合は自然治癒する可能性が高いのです。
急性裂肛の場合、食事や生活習慣の改善、便通のコントロールにより、4〜5日程度で症状が改善することが多いです。実際、外科的な治療が必要になるのは約1割程度と言われています。
しかし、自然治癒には以下の条件が必要です。
- 比較的浅い傷である
- 便通が改善される
- 肛門周囲を清潔に保てる
- 慢性化していない
慢性化した切れ痔は自然治癒が難しくなります。慢性裂肛になると、キズが次第に硬くなり、肛門が広がりにくくなってしまうのです。
どうして慢性化するのでしょうか?
それは「切れ痔の悪化サイクル」が原因です。排便時の強い痛みで排便が怖くなり、便を我慢する傾向になります。すると便秘になり、便は硬くなります。これが肛門を通る際にまた肛門を傷つけ、さらに強い痛みとなる…。このサイクルが続くと、最終的には便が通らないほど肛門が狭くなってしまうことさえあるのです。
自分でできる切れ痔の対処法と治療のポイント
切れ痔の多くは自宅でのケアで改善できます。特に急性裂肛の場合は、適切なセルフケアで数日以内に症状が軽減することが多いんです。
自分でできる効果的な対処法を3つご紹介します。
1. 肛門周囲を清潔に保つ
肛門の周囲が不衛生な状態のままでいると、切れ痔の傷から菌が入り、感染を起こす原因となります。排便後はやさしく洗浄し、清潔に保ちましょう。
ただし、ゴシゴシと強くこすると逆効果です。肛門周囲の皮膚は非常にデリケートなので、優しく洗いましょう。
2. 下痢・便秘を起こさないようにする
便の状態を整えることが、切れ痔の治療と予防の基本です。
硬い便は肛門に負担をかけ、傷を広げてしまいます。一方、下痢の場合は便に含まれる消化液が傷を刺激し、治りを遅くします。
- 食物繊維を十分に摂取する
- 水分をこまめに取る
- 規則正しい食生活を心がける
- 適度な運動を行う
これらの習慣で便通を整えることが大切です。
3. 患部周辺を温める
温めることで血行が良くなり、治癒を促進します。お風呂でゆっくり温まるか、温水につかる「坐浴」が効果的です。
坐浴は38〜40度程度のお湯に10〜15分程度浸かります。1日2〜3回行うと効果的です。
痛みが強い場合は、市販の痔疾用軟膏を使用するのも一つの方法です。
でも、こんな疑問が浮かびませんか?
「自分で治せる切れ痔と、病院に行くべき切れ痔の違いは?」
自分では治せない切れ痔の種類と受診の目安
セルフケアで対応できる切れ痔もありますが、中には専門的な治療が必要なケースもあります。どんな場合に病院を受診すべきなのでしょうか?
自分では治せない切れ痔の特徴
以下のような切れ痔は、自己治療だけでは改善が難しいことが多いです。
- 脱出性裂肛:痔核(いぼ痔)や肛門ポリープが繰り返し脱出することで生じる裂肛
- 症候性裂肛:クローン病などの全身性疾患に伴う裂肛
- 慢性化した裂肛:同じ場所が何度も切れ、傷が深くなったもの
特に慢性裂肛では、キズの内側に肛門ポリープ、外側に「見張りイボ」が形成されることがあります。さらに悪化すると肛門が硬くなり、狭窄を起こします。
病院を受診した方がいい切れ痔の症状
以下のような症状がある場合は、早めに専門医を受診しましょう。
- 1週間以上症状が改善しない
- 出血量が多い、または持続的に出血する
- 排便時以外にも痛みがある
- 排便後の痛みが長時間(数時間以上)続く
- 肛門周囲に腫れや硬結がある
- 発熱や全身倦怠感を伴う
特に排便時以外の出血は、大腸がんなど他の疾患の可能性もあるため、必ず専門医の診察を受けてください。
「出血を痔だと思って放置しておくと、がんのステージは進行しやすい」と専門医も警告しています。40歳を過ぎたら一度内視鏡検査を受けることも大切です。
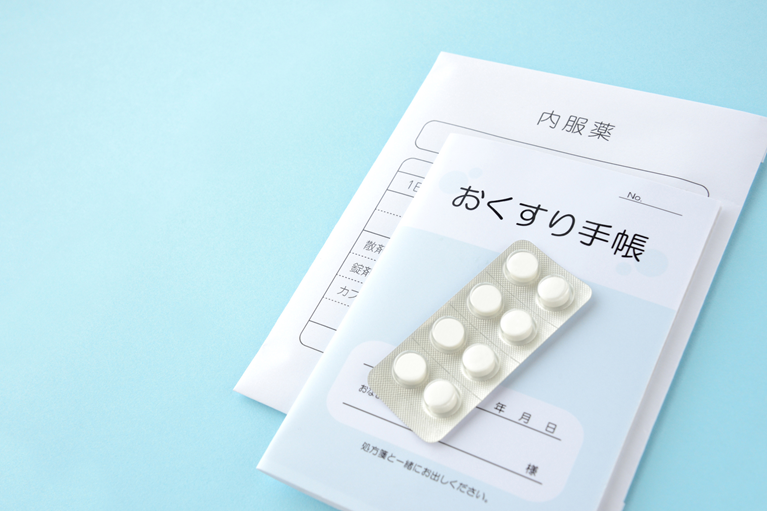
病院で行われる切れ痔の治療法とその効果
自己治療で改善しない切れ痔は、専門医による適切な治療が必要です。病院ではどのような治療が行われるのでしょうか?
薬物療法
慢性化していない切れ痔であれば、まず薬物療法が行われます。
- 軟膏・坐剤:炎症を抑え、痛みを和らげる
- 筋弛緩剤:肛門括約筋の緊張を緩和する
- 便軟化剤:便を柔らかくして排便時の痛みを軽減する
これらの薬物療法と生活習慣の改善で、多くの切れ痔は改善します。
しかし、便秘や下痢が改善されないと切れ痔が慢性化してしまうことがあります。慢性化した切れ痔では、肛門周辺の皮膚が線維化し、瘢痕化して皮膚部分が狭まって便を出しにくくなります。
外科的治療
慢性化した切れ痔や、薬物療法で改善しない場合は外科的治療が検討されます。
主な外科的治療には以下のようなものがあります。
- 用指肛門拡張術:肛門括約筋の過度の緊張を緩めるために、指を使って肛門を拡げる手術。日帰り手術が可能です。
- 側方皮下内括約筋切開術(LSIS):肛門括約筋の一部をメスで切開することで緊張を解消する手術。即効性がありますが、再発のリスクや便失禁の合併症があります。
- 裂肛切除術、肛門ポリープ切除:慢性化した切れ痔で、深い溝のようになって治りにくい状態の場合に行います。
手術は裂肛自体を治すというより、肛門をもとの広さに戻してあげることで裂肛を改善させるものです。「肛門形成術」と言われますが、適切な広さ以上に拡げすぎると便漏れを起こすこともあるため、専門医による慎重な判断が必要です。
切れ痔を放置するリスクと予防法
切れ痔を放置すると、どのようなリスクがあるのでしょうか?また、再発を防ぐためにはどうすればよいでしょうか?
切れ痔を放置するリスク
慢性の切れ痔を放置すると、以下のようなリスクがあります。
- 肛門ポリープができる:傷の内側に肉芽組織が形成され、ポリープになることがあります。
- 潰瘍ができる:傷が深くなり、潰瘍状になることがあります。
- 肛門皮垂(見張りイボ):傷の外側に皮膚のタグができることがあります。
- 肛門狭窄:肛門が狭くなり、排便がさらに困難になります。
- 感染:傷から細菌が侵入し、膿瘍を形成することがあります。
特に慢性裂肛がひどくなって潰瘍になり、その深い傷から細菌が侵入して膿瘍ができてしまうケースは侮れません。
切れ痔の予防法
切れ痔の再発を防ぐためには、以下の点に注意しましょう。
- 便通を整える:食物繊維と水分を十分に摂取し、規則正しい排便習慣を身につける
- 排便を我慢しない:便意を感じたら早めにトイレに行く
- 肛門に負担をかけない:力まずにリラックスして排便する
- 肛門周囲を清潔に保つ:優しく洗浄し、刺激を与えない
- 長時間のトイレ滞在を避ける:スマホや読書などでトイレに長居しない
これらの習慣を日常生活に取り入れることで、切れ痔の再発リスクを大幅に減らすことができます。

まとめ:切れ痔との上手な付き合い方
切れ痔は多くの方が経験する肛門疾患ですが、適切な対処で改善できることがほとんどです。この記事のポイントをまとめてみましょう。
- 急性裂肛は適切なセルフケアで4〜5日程度で自然治癒することが多い
- 自己治療のポイントは「肛門周囲の清潔保持」「便通の改善」「患部の保温」
- 1週間以上改善しない、出血が多い、排便時以外の痛みがあるなどの場合は専門医を受診する
- 慢性化した切れ痔は自然治癒しにくく、外科的治療が必要になることがある
- 予防には便通を整え、排便習慣を見直すことが重要
切れ痔の症状に気づいたら、早めの対処が大切です。恥ずかしさから放置せず、適切なケアを行いましょう。
また、40歳を過ぎたら一度内視鏡検査を受けることも重要です。肛門からの出血は痔だけでなく、大腸がんなど他の疾患の可能性もあるためです。
切れ痔でお悩みの方は、大阪消化器内科・内視鏡クリニック難波院にご相談ください。日本内視鏡学会認定の内視鏡専門医による適切な診断と治療を受けることができます。肛門科では切れ痔をはじめとする肛門疾患の治療に対応しており、女性医師も常駐していますので安心してご相談いただけます。
詳しい情報や予約方法については、大阪消化器内科・内視鏡クリニック 難波院の公式サイトをご覧ください。

著者情報
理事長 石川 嶺
経歴
| 近畿大学医学部医学科卒業 |
| 和歌山県立医科大学臨床研修センター |
| 名古屋セントラル病院(旧JR東海病院)消化器内科 |
| 近畿大学病院 消化器内科医局 |
| 石川消化器内科内視鏡クリニック開院 |







